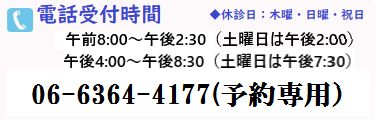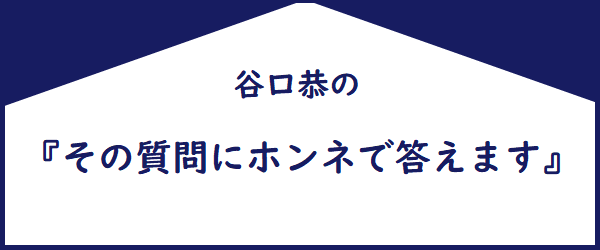マンスリーレポート
2010年8月号 『GM~踊れドクター』は総合診療の醍醐味を伝えられるか
『GM~踊れドクター』というテレビドラマが先月(2010年7月)から始まりました。
このドラマが始まることを聞いたときに私は大変驚いたのですが、その理由は「総合診療科が舞台になる」というものです。
これまでも、医師が登場するドラマというのはいくつもあったと思いますが、登場人物は、外科医であったり、救急医であったり、あるいは精神科医や法医学者であったり、と、ある意味で"わかりやすい"設定となっていました。例えば、外科医が主人公なら難易度の高い手術を完璧にやりとげるスーパー外科医がドラマになりますし(代表が『ブラックジャック』でしょう)、救急医療の現場を舞台にすれば生死の間(はざま)を描いた臨場感あふれるシーンは視聴者をひきつけます(代表は『ER』でしょうか)。また、難解な事件に挑む刑事ドラマでは、精神科医や法医学者がキーパーソンになることはよくあります。
一方、総合診療科医が日頃診ている患者というのは、診療所やクリニックであれば、複数の訴えがある患者や大病院に行く必要のない重症でない患者であり、大病院の場合は、どこに行ってもなかなか診断がつかない症例が中心になります。この場合、長時間に渡る問診と検査が中心になりますが、これでは見せ場もなくドラマになりません。総合診療科医の現場というのは、一言で言えば"ジミ"なのです。
『GM~踊れドクター』の舞台は大病院の総合診療科です。主人公の後藤医師は、アメリカで活躍していた総合診療科医であり、他の医師に分からなかった難易度の高い症例に取り組み、最終的に正しい診断をつけて患者が回復する、というのが毎回のストーリーの展開です。
これまでのストーリーを簡単に紹介しておくと、第1回は、神経内科の大御所ドクターが「ALS(筋萎縮性側索硬化症)」と診断をつけた手足が動かず呼吸困難の男性患者を、ALSではなく「キアリ奇形Ⅰ型」という脳の外傷でおこる疾患であることを後藤医師が見抜きます。ALSに合わない症状を呈していることに注目し、そこからいくつかの別の疾患の可能性を考え、最終的に正しい診断に結びつけたのです。
第2回は、意識障害で入退院を繰り返している若い女性に対し、「患者は水をよく飲む」「低い山ではなんともないのに高い山に登れば意識をなくす」、といったヒントなどから、「鎌状赤血球症」という病気にたどりつきます。
第3回は、リンパ節腫脹、尿閉(尿がでなくなること)、神経障害などを呈している30代男性患者に対し、「蚊アレルギー」があることや「最近生まれて初めてのキスをしたこと」、「血球貪食症候群があること」、などからEBウイルス感染症、さらに、EBウイルス感染症のなかでも、大変稀(まれ)で難治性の「慢性活動性EBウイルス感染症」であることをつきとめます。
私自身も、以前大学の総合診療科で外来を担当していたとき、「どこの科に行っても診断がつかない」という症例をいくつも経験しましたし、現在の太融寺町谷口医院の患者さんのなかにも「どこに行っても分からないと言われて・・・」と言って、多くの医療機関の検査データを持参して受診される人がいますから、<他の医療機関で分からなかった症例に取り組む>という医療行為は私にとっては馴染みの深いものです。(実際に正しく診断できるとは限りませんが・・・)
そのような私の立場からこのドラマを見ても、「なかなか上手くできているなぁ・・・」というのが率直な感想です。これまでの3話とも、いくつもの偶然が実際にはあり得ないほどに重なっていて、現実はこんなふうに診断がつくなんてことはないだろう、とは思うのですが、それでも「なくはないかもしれない・・・」、とも感じられます。
また、ドラマですから、正しい診断にたどりつくまでにヒントが小出しにしか出てこず、医師がみていてもストーリーの前半では病名がわからないように構成されていて、この点も「上手くできているなぁ・・」と感じます。例えば、先に紹介した第3回の話であれば、もしも「蚊アレルギー」と「血球貪食症候群」が初めからわかっていれば、おそらく医師の大半はドラマの前半で診断がつけられたでしょう。
と思って調べてみると、このドラマの監修をされているのが千葉大学医学部附属病院総合診療科の生坂政臣教授でした。生坂教授は、総合診療をおこなう者であれば知らない者はいないこの世界で最も著名な医師のひとりです。
なるほど、生坂先生が監修されているからこのような構成になっているのか・・・。改めてドラマを振り返ってみると、このように感じるシーンがこのドラマにはいくつかあります。
まず、先にも述べたように、一般の人だけでなく、医師が見ていても、正しい診断名は最後の方にならないと分からないような構成にしていることです。
次に、総合診療科医に対して、病院事務長が毎回のように言う「総合診療科は病院の赤字部門」というセリフです。実際、大病院の総合診療科の大半は利益がでず、そのために閉鎖に追い込まれているところもあります。(下記コラムも参照ください) 私の考え過ぎかもしれませんが、総合診療科は利益は出ないけれども日本の医療に必要なんですよ、ということを生坂先生は訴えたかったのではないでしょうか。
もうひとつ、このドラマにでてくる総合診療科医がやる気のない医師ばかりの設定にしていることも興味深いと言えます。主人公の後藤医師でさえ、「本職は医師ではなくダンサー」と公言しますし、潔癖症で患者に触れることができません。他の医師は、ガッツのあるひとりの若い女性の研修医を除けば、問題を抱えた医師ばかりです。登場人物をこのような設定にしているのは生坂先生の"自虐的"とも言える謙虚さではないかと私には感じられます。
さて、このドラマを見て、どれだけの人がおもしろいと感じているのでしょうか。私自身は、ドラマの医師たちと同じ総合診療科の医局に所属している医師ですから、「後藤医師よりも早く正しい診断にたどりついてやるぞ!」という気持ちでストーリーを追いかけているのですが、この<正しい診断にたどりつく>というのは、(不謹慎な言い方ですが)どこか推理小説を読むような楽しさがあります。複雑怪奇な凶悪事件の謎を解く刑事の醍醐味に似ているかもしれません。
医師や医療従事者でない人も、そのように「犯人探し」や「トリック探し」に似た「正しい診断にいたる過程」を推理ドラマのような観点から見ることができれば、このドラマを楽しめるのではないかと思います。
ところで、このドラマは医療ドラマでありながら<コメディ>でもあります。第1回をみたときの私の率直な感想は、「シリアスな総合診療のドラマにするか完全なコメディにするかどちらかにしてほしい、これは中途半端だ・・・」、というものでしたが、第2回、第3回と回を重ねるにつれて、コメディとしてもこのドラマを楽しめるようになってきました。
ドラマの細かいところに笑えるシーンがいくつも登場するのですが、やはり何と言っても一番注目すべきは主人公の後藤医師でしょう。極度な潔癖症から患者には一切触れず、誰もいない部屋(医局)でひとりでムーンウォークをしながら症例について思いを巡らせ、診断がつくと突然「ファイアー!」と大声を出すのです。
後藤医師を演じるのは、元少年隊の東山紀之さんなのですが、後藤医師の設定も、「自分に似ていると言われる東山紀之に憧れ、かつてアイドルグループ「アミー&ゴー」としてデビューし、『仮面ぶどう狩り』という歌を出したが・・・」、ということになっています。第1回の冒頭では、少年隊の『仮面舞踏会』のビデオクリップが使われていました。私と同世代の人にはたいへんなつかしく感じられたのではないでしょうか。
それにしても、このドラマを見始めてから、私の頭から『仮面舞踏会』の旋律がこびりついて離れないのですが何とかならないでしょうか・・・。
参考:
メディカルエッセイ第76回(2009年5月) 「大学病院の総合診療科の危機 その1」
メディカルエッセイ第77回(2009年6月) 「大学病院の総合診療科の危機 その2」
このドラマが始まることを聞いたときに私は大変驚いたのですが、その理由は「総合診療科が舞台になる」というものです。
これまでも、医師が登場するドラマというのはいくつもあったと思いますが、登場人物は、外科医であったり、救急医であったり、あるいは精神科医や法医学者であったり、と、ある意味で"わかりやすい"設定となっていました。例えば、外科医が主人公なら難易度の高い手術を完璧にやりとげるスーパー外科医がドラマになりますし(代表が『ブラックジャック』でしょう)、救急医療の現場を舞台にすれば生死の間(はざま)を描いた臨場感あふれるシーンは視聴者をひきつけます(代表は『ER』でしょうか)。また、難解な事件に挑む刑事ドラマでは、精神科医や法医学者がキーパーソンになることはよくあります。
一方、総合診療科医が日頃診ている患者というのは、診療所やクリニックであれば、複数の訴えがある患者や大病院に行く必要のない重症でない患者であり、大病院の場合は、どこに行ってもなかなか診断がつかない症例が中心になります。この場合、長時間に渡る問診と検査が中心になりますが、これでは見せ場もなくドラマになりません。総合診療科医の現場というのは、一言で言えば"ジミ"なのです。
『GM~踊れドクター』の舞台は大病院の総合診療科です。主人公の後藤医師は、アメリカで活躍していた総合診療科医であり、他の医師に分からなかった難易度の高い症例に取り組み、最終的に正しい診断をつけて患者が回復する、というのが毎回のストーリーの展開です。
これまでのストーリーを簡単に紹介しておくと、第1回は、神経内科の大御所ドクターが「ALS(筋萎縮性側索硬化症)」と診断をつけた手足が動かず呼吸困難の男性患者を、ALSではなく「キアリ奇形Ⅰ型」という脳の外傷でおこる疾患であることを後藤医師が見抜きます。ALSに合わない症状を呈していることに注目し、そこからいくつかの別の疾患の可能性を考え、最終的に正しい診断に結びつけたのです。
第2回は、意識障害で入退院を繰り返している若い女性に対し、「患者は水をよく飲む」「低い山ではなんともないのに高い山に登れば意識をなくす」、といったヒントなどから、「鎌状赤血球症」という病気にたどりつきます。
第3回は、リンパ節腫脹、尿閉(尿がでなくなること)、神経障害などを呈している30代男性患者に対し、「蚊アレルギー」があることや「最近生まれて初めてのキスをしたこと」、「血球貪食症候群があること」、などからEBウイルス感染症、さらに、EBウイルス感染症のなかでも、大変稀(まれ)で難治性の「慢性活動性EBウイルス感染症」であることをつきとめます。
私自身も、以前大学の総合診療科で外来を担当していたとき、「どこの科に行っても診断がつかない」という症例をいくつも経験しましたし、現在の太融寺町谷口医院の患者さんのなかにも「どこに行っても分からないと言われて・・・」と言って、多くの医療機関の検査データを持参して受診される人がいますから、<他の医療機関で分からなかった症例に取り組む>という医療行為は私にとっては馴染みの深いものです。(実際に正しく診断できるとは限りませんが・・・)
そのような私の立場からこのドラマを見ても、「なかなか上手くできているなぁ・・・」というのが率直な感想です。これまでの3話とも、いくつもの偶然が実際にはあり得ないほどに重なっていて、現実はこんなふうに診断がつくなんてことはないだろう、とは思うのですが、それでも「なくはないかもしれない・・・」、とも感じられます。
また、ドラマですから、正しい診断にたどりつくまでにヒントが小出しにしか出てこず、医師がみていてもストーリーの前半では病名がわからないように構成されていて、この点も「上手くできているなぁ・・」と感じます。例えば、先に紹介した第3回の話であれば、もしも「蚊アレルギー」と「血球貪食症候群」が初めからわかっていれば、おそらく医師の大半はドラマの前半で診断がつけられたでしょう。
と思って調べてみると、このドラマの監修をされているのが千葉大学医学部附属病院総合診療科の生坂政臣教授でした。生坂教授は、総合診療をおこなう者であれば知らない者はいないこの世界で最も著名な医師のひとりです。
なるほど、生坂先生が監修されているからこのような構成になっているのか・・・。改めてドラマを振り返ってみると、このように感じるシーンがこのドラマにはいくつかあります。
まず、先にも述べたように、一般の人だけでなく、医師が見ていても、正しい診断名は最後の方にならないと分からないような構成にしていることです。
次に、総合診療科医に対して、病院事務長が毎回のように言う「総合診療科は病院の赤字部門」というセリフです。実際、大病院の総合診療科の大半は利益がでず、そのために閉鎖に追い込まれているところもあります。(下記コラムも参照ください) 私の考え過ぎかもしれませんが、総合診療科は利益は出ないけれども日本の医療に必要なんですよ、ということを生坂先生は訴えたかったのではないでしょうか。
もうひとつ、このドラマにでてくる総合診療科医がやる気のない医師ばかりの設定にしていることも興味深いと言えます。主人公の後藤医師でさえ、「本職は医師ではなくダンサー」と公言しますし、潔癖症で患者に触れることができません。他の医師は、ガッツのあるひとりの若い女性の研修医を除けば、問題を抱えた医師ばかりです。登場人物をこのような設定にしているのは生坂先生の"自虐的"とも言える謙虚さではないかと私には感じられます。
さて、このドラマを見て、どれだけの人がおもしろいと感じているのでしょうか。私自身は、ドラマの医師たちと同じ総合診療科の医局に所属している医師ですから、「後藤医師よりも早く正しい診断にたどりついてやるぞ!」という気持ちでストーリーを追いかけているのですが、この<正しい診断にたどりつく>というのは、(不謹慎な言い方ですが)どこか推理小説を読むような楽しさがあります。複雑怪奇な凶悪事件の謎を解く刑事の醍醐味に似ているかもしれません。
医師や医療従事者でない人も、そのように「犯人探し」や「トリック探し」に似た「正しい診断にいたる過程」を推理ドラマのような観点から見ることができれば、このドラマを楽しめるのではないかと思います。
ところで、このドラマは医療ドラマでありながら<コメディ>でもあります。第1回をみたときの私の率直な感想は、「シリアスな総合診療のドラマにするか完全なコメディにするかどちらかにしてほしい、これは中途半端だ・・・」、というものでしたが、第2回、第3回と回を重ねるにつれて、コメディとしてもこのドラマを楽しめるようになってきました。
ドラマの細かいところに笑えるシーンがいくつも登場するのですが、やはり何と言っても一番注目すべきは主人公の後藤医師でしょう。極度な潔癖症から患者には一切触れず、誰もいない部屋(医局)でひとりでムーンウォークをしながら症例について思いを巡らせ、診断がつくと突然「ファイアー!」と大声を出すのです。
後藤医師を演じるのは、元少年隊の東山紀之さんなのですが、後藤医師の設定も、「自分に似ていると言われる東山紀之に憧れ、かつてアイドルグループ「アミー&ゴー」としてデビューし、『仮面ぶどう狩り』という歌を出したが・・・」、ということになっています。第1回の冒頭では、少年隊の『仮面舞踏会』のビデオクリップが使われていました。私と同世代の人にはたいへんなつかしく感じられたのではないでしょうか。
それにしても、このドラマを見始めてから、私の頭から『仮面舞踏会』の旋律がこびりついて離れないのですが何とかならないでしょうか・・・。
参考:
メディカルエッセイ第76回(2009年5月) 「大学病院の総合診療科の危機 その1」
メディカルエッセイ第77回(2009年6月) 「大学病院の総合診療科の危機 その2」