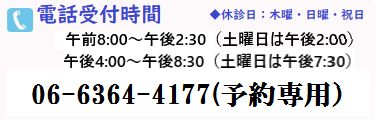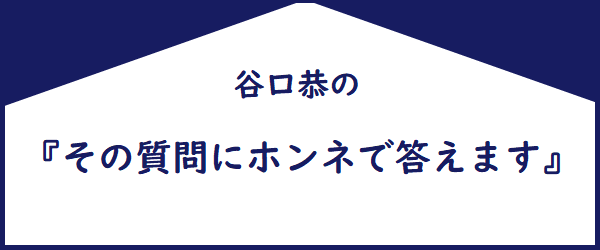マンスリーレポート
2012年10月号 山中先生から学んだこととこれからも学びたいこと
ビジョンを持って楽しく研究しましょう。そして薬理学教室の美味しいコーヒーを一緒に飲みましょう。
一字一句同じではないでしょうが、これは1999年の(たぶん)3月、大阪市立大学医学部の大教室の教壇で山中伸弥先生が我々学生に対して話された言葉です。
2012年10月8日、ノーベル医学・生理学賞を受賞された京都大学の山中教授は、神戸大学医学部を卒業された後、大阪市立大学医学部整形外科に入局され、その後同大学薬理学教室に入られ、1996年から1999年11月まで薬理学教室の助手として、研究に教育にと活躍されていました。
私が大阪市立大学医学部に入学したのは1996年、薬理学を学んだのは3回生のときですから、1998年4月から1999年3月までの一年間、薬理学の授業のうち何コマかは山中先生に教えてもらっていました。山中先生の講義は非常にむつかしく、配布されるプリントはほとんどが英語であり、私の苦手な分野だったこともあり、テスト勉強に苦しんだことを覚えています。ちなみに、当時、山中先生が大学医学部で講義されていたのは、(当然ですが)iPS細胞についてではなく、循環薬理学だったと記憶しています。
当時の大阪市立大学医学部では、4回生の前半は講義や実習はなく、基礎医学系の研究室に入って特定のテーマについての研究をすることになっていました。2~4名くらいのグループに分かれ、それぞれのグループはどこかの基礎医学系の教室に所属し、指導教官の元で研究をおこなうことになります。
例えば、第一解剖学教室では3つの研究班があり、3つの班の指導教官はA先生、B先生、C先生の3人で、各班の定員は2~4名、などと決められており、学生は希望する班を選ぶ、というわけです。基礎医学系の教室ですから、解剖学以外に、生理学、生化学、薬理学、細菌学、などがあります。山中先生は薬理学教室の3つの班の1つの指導教官だったと記憶しています。
各学生がどの班を選択するかにあたり、オリエンテーションのようなものが開かれ、この場で各教室の指導教官の先生方が学生を前に、どのような研究ができるかを話します。せいぜい3~4ヶ月の研究ですが、学生からすれば初めての本格的な研究ができるわけですし、指導する教員の立場からしてもできるだけ優秀な学生に来てもらいたい(やる気のない学生には来てもらいたくない)わけですから、このオリエンテーションは双方にとって大切な場となります。
冒頭で紹介した山中先生の言葉は、このオリエンテーションで話された最後の締めの言葉です。なぜ、私が山中先生の言葉を今でも覚えているのか、これは私にとっても不思議です。なにしろ、他の先生の言葉は一切記憶にないのですから。
当時の私は、研究が自分に向いていないことをひしひしと感じており、医学部を続ける自信を喪失していました。入学当時は、臨床家を目指すのではなく基礎医学の研究をやりたいと考えていた私は、入学直後から必死に勉強していたつもりでしたが、どうも研究をおこなうにはセンスも能力もないのではないかということに気づき始め、それを確証するようになっていきました。
この頃の私は、授業にはかろうじて出席していましたが、生活の中心はアルバイトになっていました。複数のアルバイトに精を出し、土日におこなっていたワゴンセールの販売では西日本全域の出張もこなしていました。複数のアルバイトをおこなうようになると、自然と知人が増えていきます。そのなかで、私はいろんな病気で悩んでいる人と知り合うこととなり、また、医療機関でイヤな思いをした、という人たちの話を聞くこととなり、こういった経験があって、研究ではなく臨床家として将来は患者さんと接していく道を選択することを決意しました。
そんな当時の私にとって、基礎医学系の研究というのは「過去のもの」という感じがして取り組む気力が起こりませんでした。山中先生のエネルギッシュな話も、印象的だったとはいえ、当時の私には「無理だろう」という気持ちが先行したのです。しかし、何らかの基礎医学の研究班に入ってレポートを書かねば進級ができません。私が選択したのは公衆衛生学教室のある班で、研究内容は「老人ホームで入居者から話を聞いて統計処理をおこなう」というものでした。社会学部出身の私にとってこれは得意分野です。社会学のフィールドワークの感覚でできると感じ、実際に研究は特に苦労もなくできました。
冒頭で紹介した山中先生の言葉はなぜかその後も心に残っていたのですが、その後先生を見かけることがないな、と感じていたら、その年の終わりには大学を辞められたと聞いて驚いたことを記憶しています。
その後私は医学部を卒業し、研修医となり、研修後タイに渡り、帰国後は大学に戻り総合診療センターに所属することになり、臨床の道を進んでいきました。基礎医学の研究に対する未練がまったくなくなったわけではありませんが、自分に向いているのは基礎医学ではなく臨床であることをこの頃にはすでに確信していました。
久しぶりに山中先生の名前を聞いたのは2006年でした。著明な医学誌『Cell』に「マウスのiPS細胞を確立した」ことを発表されたのです。iPS細胞については、いろんなところで解説されていますからここでは述べませんが、このときに私が感じたことは2つあります。まず先生の所属が京都大学になっていたことです。詳しい経緯は分からないけれど、おそらく京都大学の方から引っ張られて移られたのだろう、と感じました。もうひとつは、iPSというネーミングが、おそらくiPodをもじったのでしょうけれど、ユニークな山中先生らしいというか、山中先生が名づけたに違いない、と感じました。
その後、山中先生は国内外の著名な賞を次々と受賞され、医学関連の雑誌やサイトだけでなく、全国紙の一面にも登場されるようになります。研究内容だけでなく、山中先生のパーソナリティや過去のエピソードなどにも触れている記事が増えてきました。そのような記事を目にするようになり、私にとって大変意外に感じられる一面もでてきました。
それまでの私の山中先生に対するイメージは、エネルギッシュでユーモアのセンスに富んだアメリカ帰りの超エリート、というものでした。しかし、先生についてのエピソードを読んでみると、医学部卒業後は整形外科の臨床医を目指したが、手術に時間がかかり指導医から才能がないと言われ基礎医学(薬理学)に転向した。アメリカで研究をおこなったまではいいが、帰国後アメリカのように自由に研究できないことから「うつ」状態となり、研究を諦め臨床に戻ることをほぼ決意していた。そんななか、奈良先端科学技術大学院大学の公募に(引っ張られたのではなく)自ら応募して助教授に就任された、などと書かれています。
つい最近知ったのですが、山中先生は若い世代に講演をされるときに「人間万事塞翁が馬」という故事を引き合いに出されることがあるそうです。私の山中先生に対する過去のイメージからはこの故事はマッチしないのですが、臨床家として苦労したこと、研究を半ば諦めかけたときに奈良先端科学技術大学大学院で道が開けたことなどを考えるとこの故事はすっと腑に落ちます。
山中先生自身が話されているように、iPS細胞が人類に役立つようになるにはまだ時間がかかります。これからは今まで以上の苦労をなさるかもしれません。山中先生は今もスポーツマンでフルマラソンにも参加されているそうです。きっとこれからの研究も、マラソンのように、少々ライバルに抜かれても、調子が上がらずにしんどくなっても、「人間万事塞翁が馬」を思い出し、ビジョンを目標に進まれることでしょう。
そんな山中先生から、これからも学ぶことがたくさんありそうです。
一字一句同じではないでしょうが、これは1999年の(たぶん)3月、大阪市立大学医学部の大教室の教壇で山中伸弥先生が我々学生に対して話された言葉です。
2012年10月8日、ノーベル医学・生理学賞を受賞された京都大学の山中教授は、神戸大学医学部を卒業された後、大阪市立大学医学部整形外科に入局され、その後同大学薬理学教室に入られ、1996年から1999年11月まで薬理学教室の助手として、研究に教育にと活躍されていました。
私が大阪市立大学医学部に入学したのは1996年、薬理学を学んだのは3回生のときですから、1998年4月から1999年3月までの一年間、薬理学の授業のうち何コマかは山中先生に教えてもらっていました。山中先生の講義は非常にむつかしく、配布されるプリントはほとんどが英語であり、私の苦手な分野だったこともあり、テスト勉強に苦しんだことを覚えています。ちなみに、当時、山中先生が大学医学部で講義されていたのは、(当然ですが)iPS細胞についてではなく、循環薬理学だったと記憶しています。
当時の大阪市立大学医学部では、4回生の前半は講義や実習はなく、基礎医学系の研究室に入って特定のテーマについての研究をすることになっていました。2~4名くらいのグループに分かれ、それぞれのグループはどこかの基礎医学系の教室に所属し、指導教官の元で研究をおこなうことになります。
例えば、第一解剖学教室では3つの研究班があり、3つの班の指導教官はA先生、B先生、C先生の3人で、各班の定員は2~4名、などと決められており、学生は希望する班を選ぶ、というわけです。基礎医学系の教室ですから、解剖学以外に、生理学、生化学、薬理学、細菌学、などがあります。山中先生は薬理学教室の3つの班の1つの指導教官だったと記憶しています。
各学生がどの班を選択するかにあたり、オリエンテーションのようなものが開かれ、この場で各教室の指導教官の先生方が学生を前に、どのような研究ができるかを話します。せいぜい3~4ヶ月の研究ですが、学生からすれば初めての本格的な研究ができるわけですし、指導する教員の立場からしてもできるだけ優秀な学生に来てもらいたい(やる気のない学生には来てもらいたくない)わけですから、このオリエンテーションは双方にとって大切な場となります。
冒頭で紹介した山中先生の言葉は、このオリエンテーションで話された最後の締めの言葉です。なぜ、私が山中先生の言葉を今でも覚えているのか、これは私にとっても不思議です。なにしろ、他の先生の言葉は一切記憶にないのですから。
当時の私は、研究が自分に向いていないことをひしひしと感じており、医学部を続ける自信を喪失していました。入学当時は、臨床家を目指すのではなく基礎医学の研究をやりたいと考えていた私は、入学直後から必死に勉強していたつもりでしたが、どうも研究をおこなうにはセンスも能力もないのではないかということに気づき始め、それを確証するようになっていきました。
この頃の私は、授業にはかろうじて出席していましたが、生活の中心はアルバイトになっていました。複数のアルバイトに精を出し、土日におこなっていたワゴンセールの販売では西日本全域の出張もこなしていました。複数のアルバイトをおこなうようになると、自然と知人が増えていきます。そのなかで、私はいろんな病気で悩んでいる人と知り合うこととなり、また、医療機関でイヤな思いをした、という人たちの話を聞くこととなり、こういった経験があって、研究ではなく臨床家として将来は患者さんと接していく道を選択することを決意しました。
そんな当時の私にとって、基礎医学系の研究というのは「過去のもの」という感じがして取り組む気力が起こりませんでした。山中先生のエネルギッシュな話も、印象的だったとはいえ、当時の私には「無理だろう」という気持ちが先行したのです。しかし、何らかの基礎医学の研究班に入ってレポートを書かねば進級ができません。私が選択したのは公衆衛生学教室のある班で、研究内容は「老人ホームで入居者から話を聞いて統計処理をおこなう」というものでした。社会学部出身の私にとってこれは得意分野です。社会学のフィールドワークの感覚でできると感じ、実際に研究は特に苦労もなくできました。
冒頭で紹介した山中先生の言葉はなぜかその後も心に残っていたのですが、その後先生を見かけることがないな、と感じていたら、その年の終わりには大学を辞められたと聞いて驚いたことを記憶しています。
その後私は医学部を卒業し、研修医となり、研修後タイに渡り、帰国後は大学に戻り総合診療センターに所属することになり、臨床の道を進んでいきました。基礎医学の研究に対する未練がまったくなくなったわけではありませんが、自分に向いているのは基礎医学ではなく臨床であることをこの頃にはすでに確信していました。
久しぶりに山中先生の名前を聞いたのは2006年でした。著明な医学誌『Cell』に「マウスのiPS細胞を確立した」ことを発表されたのです。iPS細胞については、いろんなところで解説されていますからここでは述べませんが、このときに私が感じたことは2つあります。まず先生の所属が京都大学になっていたことです。詳しい経緯は分からないけれど、おそらく京都大学の方から引っ張られて移られたのだろう、と感じました。もうひとつは、iPSというネーミングが、おそらくiPodをもじったのでしょうけれど、ユニークな山中先生らしいというか、山中先生が名づけたに違いない、と感じました。
その後、山中先生は国内外の著名な賞を次々と受賞され、医学関連の雑誌やサイトだけでなく、全国紙の一面にも登場されるようになります。研究内容だけでなく、山中先生のパーソナリティや過去のエピソードなどにも触れている記事が増えてきました。そのような記事を目にするようになり、私にとって大変意外に感じられる一面もでてきました。
それまでの私の山中先生に対するイメージは、エネルギッシュでユーモアのセンスに富んだアメリカ帰りの超エリート、というものでした。しかし、先生についてのエピソードを読んでみると、医学部卒業後は整形外科の臨床医を目指したが、手術に時間がかかり指導医から才能がないと言われ基礎医学(薬理学)に転向した。アメリカで研究をおこなったまではいいが、帰国後アメリカのように自由に研究できないことから「うつ」状態となり、研究を諦め臨床に戻ることをほぼ決意していた。そんななか、奈良先端科学技術大学院大学の公募に(引っ張られたのではなく)自ら応募して助教授に就任された、などと書かれています。
つい最近知ったのですが、山中先生は若い世代に講演をされるときに「人間万事塞翁が馬」という故事を引き合いに出されることがあるそうです。私の山中先生に対する過去のイメージからはこの故事はマッチしないのですが、臨床家として苦労したこと、研究を半ば諦めかけたときに奈良先端科学技術大学大学院で道が開けたことなどを考えるとこの故事はすっと腑に落ちます。
山中先生自身が話されているように、iPS細胞が人類に役立つようになるにはまだ時間がかかります。これからは今まで以上の苦労をなさるかもしれません。山中先生は今もスポーツマンでフルマラソンにも参加されているそうです。きっとこれからの研究も、マラソンのように、少々ライバルに抜かれても、調子が上がらずにしんどくなっても、「人間万事塞翁が馬」を思い出し、ビジョンを目標に進まれることでしょう。
そんな山中先生から、これからも学ぶことがたくさんありそうです。