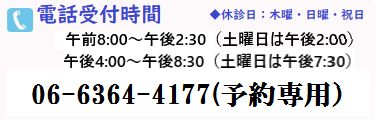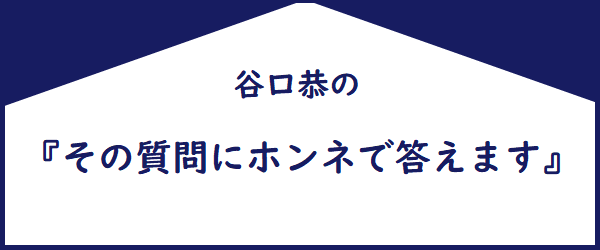メディカルエッセイ
3 差別される病気 2004/3/19
病気になると様々な苦悩が伴うことが多いと言えますが、医療従事者から軽視されがちと私が感じることのひとつに「差別」という苦悩があります。病気の苦悩と言えば、痛み、呼吸苦、不快感、痒み、あるいは不安、抑うつなどもそうでしょうが、なかなか「差別」という苦悩については、大きく取り上げられることは少ないように感じます。
この理由として、まず我々医師や看護師などの医療従事者が「差別」に対する教育を受けていないということがあげられます。痛みや痒みに対しては、薬剤もありますし、患者さんの訴えがあればすぐに対処しようとします。ところが、「差別」に対しては、患者さんの訴えを聞くことがあっても、現場の医療従事者はほとんど無力です。
次に、患者さんが「差別」に対しては、なかなかその苦悩を訴えないということがあります。いくら差別に悩んでいたとしても、医師や看護師との間に、ある程度の信頼関係ができるまで言い出し辛いのです。やっとの思いでその苦悩を口にしたとしても、なかなかきちんと聞いてくれなかったり、初めから相手にされなかったりということも珍しくないようです。
では、医者は患者の「差別」について取り組まなくてもいいのでしょうか。そんなはずは絶対にありません。そもそも医療というのは、身体面だけをみているだけでは不十分なはずです。健康というのは、身体だけでなく、精神的、社会的にも健康でなければならないはずです。
病気であるがゆえに「差別」を受けているとすれば、これは健康からはほど遠い状態にあるわけです。たしかに、上にあげた理由もあり、患者の「差別」という苦悩に対する対処はむつかしいのですが、医師である以上は、病気に伴うすべての苦悩について取り組まなくてはならない、私はそう考えます。
では、どんな病気が「差別」されるのでしょうか。まずひとつは、結核やハンセン病などの感染症があげられます。結核患者は現在でも隔離されることが多いですし、ハンセン病などは、見た目で分かることもあり、歴史的に差別されてきた事実があります。昨年、九州のある旅館で、ハンセン病の患者の宿泊を拒否したという事件もこのことを物語っています。
身体障害者も差別されることが少なくありません。小学校のとき、小児麻痺の生徒がいじめられたり、ばかにされたりといったいわれのない差別を受けていたことを思い出します。大人でも、例えば、一生車椅子を強いられた人は、健常人からは分からないようなところで様々な差別を受けているという現実があります。
別のところでも書きましたが、皮膚疾患もそうです。見た目ですぐに病気とわかる疾患は何かと差別の対象になるものです。実は私が医師になりたいと思った動機のひとつに、「差別に取り組みたい」というのがあります。私は、皮膚疾患もそうですが、もうひとつ、差別に取り組みたい疾患が、「性感染症」です。
AIDS患者が差別されている現状は明らかでしょう。私は今年の夏に、タイ国にあるパバナプ寺というAIDS患者がおよそ400人ほど収容されている施設にボランティアに行く予定ですが、日本よりも断然患者数の多いタイ国でさえ、AIDS患者は差別されています。家族からも見放されることさえ少なくありません。
私は一昨年もその施設に行ったのですが、ボランティアをしている医師からこのようなことを聞きました。レントゲン撮影のできないその施設で、どうしても胸部レントゲンを撮る必要のある患者がいて、その医師は近くの病院にその患者を送ったそうです。ところが送り先の病院では、その患者がAIDSであるという理由で撮影を拒否したというのです。そしてこのようなことは日常茶飯事だというのです。
差別される性感染症は何もAIDSだけではありません。すべての性感染症が差別の対象となっているといってもいいでしょう。クラミジアでもヘルペスでも感染すると、患者さんはなかなか人にはそのことを告げられません。勇気をだして病院に行ったとしても、なかなか堂々と症状を訴えることはできません。
そして、性感染症は、身体障害や通常の皮膚疾患など、他の社会的に差別を受けている疾患と大きく異なる点があります。それは医療従事者からも差別的な発言をされることがあるということです。誰にも言えない病気にかかり、やっとの思いで病院に行っているのに、その病院で医者や看護師から差別的な発言をされることも少なくないのです。「不潔なことをするからそんなことになるんだ」とか「君みたいな女がいるから世の中の性病はなくならないんだ」とか、そんなことを言われることもあるのです。
私が実際にある女性から聞いた話を紹介しましょう。その女性は、私の知人の知人で、あるとき数人で食事をしていたときに、たまたま席が横になったので話すことになりました。当時私は医学部の学生で、まだ臨床医学をほとんど知らない頃でした。話の流れで自分は医学部生だという話題になったときに、彼女は私にだけ聞こえるように身の上話を始めました。
彼女は数年前に、ある風俗店で働いていたというのです。風俗店で働くということは、言うまでもなく、様々な性感染のリスクがあります。特に症状が出たわけでもないのですが、性感染が心配になった彼女は、いくつかのクリニックを受診したそうです。
彼女は、医師や看護婦には、「なぜ受診したか」ということを正直に話しました。彼女は、現在の仕事のことも話しました。社会的には何かと差別の対象になる仕事ですが、医療従事者ならそのまま受け止めてくれて相談にのってくれると考えたのです。
ところが、彼女がかかったクリニックの医療従事者は全員、冷淡な態度をとったというのです。
「そんな仕事をしているのが悪いのです。」「すぐに仕事をやめなさい。」
どこへ行ってもそのように言われて、なぜ仕事を続けなければならないかという点については、誰も聞いてくれなかったというのです。彼女にとって、性感染のことを真剣に相談できるのは医療機関をおいて他にはなかったのです。本当は彼女だって仕事のことは誰にも言いたくなかったのです。
それに、彼女は好き好んでそのような仕事をしているわけではないのです。彼女の場合、両親の残した巨額の借金を返済するために、仕方なく働いていたそうです。もちろんこれは本当のことかどうかは分かりませんが、少なくとも私が聞いた印象では、高収入が得られるからとか、嫌いな仕事じゃないから、とかそんな理由で働いていたとは思えませんでした。
性感染症、これほどまで差別の対象となる病気は他にないのではないでしょうか。誰にも言えずにひとりで悩まなくてはならず、さらに医療機関でさえも差別的な発言を受けるのです。
彼女は、なぜ言う必要のない過去の嫌な思いを私に話したのでしょうか。現在は借金を返済し終えており、忘れたいことをわざわざ話す必要などなかったはずです。
私はこのように考えました。「私も数年先には医師になる以上、性感染症の患者をみることがあるかもしれない。私には他の患者と同様、差別することなく診てほしい。」、彼女はそれを伝えたかったのではないかと思うのです。
私は、そのとき、彼女の連絡先どころか名前も聞きませんでした。今ではどこにいるのかも分かりません。これから会うこともないでしょう。
けれども、私はこのことを語っているときの彼女の目を忘れることができません。そしてこのエピソードが、私が性感染症に取り組みたいと思った最大の理由なのです。
ちなみに性感染症を扱っている科というのは、まず性病科が筆頭にきますが、「性病科」の看板をあげているクリニックはほとんどありません。実際は、皮膚科、泌尿器科、婦人科などが、部分的にみているというのが現状です。
「部分的に」というのは、例えば、婦人科では男性はみませんし、皮膚科ではヘルペスやクラミジア、梅毒といった皮膚に症状の出る疾患は得意としますが、クラミジアや淋病といった疾患については通常みることはありません。これとは逆に、泌尿器科では、クラミジアや淋病以外の疾患はあまり得意としていません。
ところが、患者さんの立場にたったときに、これは相当不便です。というのは、まずひとつめに性感染というのは、重複感染していることが多いという問題があります。例えば、クラミジアとヘルペスに同時に感染したなどという場合、クラミジアは泌尿器科で、ヘルペスは皮膚科でというふうに、複数の医療機関を受診しなければならないのです。
もうひとつ、性感染は、パートナーを同時に治療しなければ意味がありません。勇気を出して、ふたりで婦人科に行っても、男性はみてくれないのです。
私は、あらゆる性感染症をパートナーも含めてトータルで治療していく必要があると考えています。
このような経緯があって、私は性感染症をトータルにみることのできる皮膚科医をめざそうと考えたわけです。
この理由として、まず我々医師や看護師などの医療従事者が「差別」に対する教育を受けていないということがあげられます。痛みや痒みに対しては、薬剤もありますし、患者さんの訴えがあればすぐに対処しようとします。ところが、「差別」に対しては、患者さんの訴えを聞くことがあっても、現場の医療従事者はほとんど無力です。
次に、患者さんが「差別」に対しては、なかなかその苦悩を訴えないということがあります。いくら差別に悩んでいたとしても、医師や看護師との間に、ある程度の信頼関係ができるまで言い出し辛いのです。やっとの思いでその苦悩を口にしたとしても、なかなかきちんと聞いてくれなかったり、初めから相手にされなかったりということも珍しくないようです。
では、医者は患者の「差別」について取り組まなくてもいいのでしょうか。そんなはずは絶対にありません。そもそも医療というのは、身体面だけをみているだけでは不十分なはずです。健康というのは、身体だけでなく、精神的、社会的にも健康でなければならないはずです。
病気であるがゆえに「差別」を受けているとすれば、これは健康からはほど遠い状態にあるわけです。たしかに、上にあげた理由もあり、患者の「差別」という苦悩に対する対処はむつかしいのですが、医師である以上は、病気に伴うすべての苦悩について取り組まなくてはならない、私はそう考えます。
では、どんな病気が「差別」されるのでしょうか。まずひとつは、結核やハンセン病などの感染症があげられます。結核患者は現在でも隔離されることが多いですし、ハンセン病などは、見た目で分かることもあり、歴史的に差別されてきた事実があります。昨年、九州のある旅館で、ハンセン病の患者の宿泊を拒否したという事件もこのことを物語っています。
身体障害者も差別されることが少なくありません。小学校のとき、小児麻痺の生徒がいじめられたり、ばかにされたりといったいわれのない差別を受けていたことを思い出します。大人でも、例えば、一生車椅子を強いられた人は、健常人からは分からないようなところで様々な差別を受けているという現実があります。
別のところでも書きましたが、皮膚疾患もそうです。見た目ですぐに病気とわかる疾患は何かと差別の対象になるものです。実は私が医師になりたいと思った動機のひとつに、「差別に取り組みたい」というのがあります。私は、皮膚疾患もそうですが、もうひとつ、差別に取り組みたい疾患が、「性感染症」です。
AIDS患者が差別されている現状は明らかでしょう。私は今年の夏に、タイ国にあるパバナプ寺というAIDS患者がおよそ400人ほど収容されている施設にボランティアに行く予定ですが、日本よりも断然患者数の多いタイ国でさえ、AIDS患者は差別されています。家族からも見放されることさえ少なくありません。
私は一昨年もその施設に行ったのですが、ボランティアをしている医師からこのようなことを聞きました。レントゲン撮影のできないその施設で、どうしても胸部レントゲンを撮る必要のある患者がいて、その医師は近くの病院にその患者を送ったそうです。ところが送り先の病院では、その患者がAIDSであるという理由で撮影を拒否したというのです。そしてこのようなことは日常茶飯事だというのです。
差別される性感染症は何もAIDSだけではありません。すべての性感染症が差別の対象となっているといってもいいでしょう。クラミジアでもヘルペスでも感染すると、患者さんはなかなか人にはそのことを告げられません。勇気をだして病院に行ったとしても、なかなか堂々と症状を訴えることはできません。
そして、性感染症は、身体障害や通常の皮膚疾患など、他の社会的に差別を受けている疾患と大きく異なる点があります。それは医療従事者からも差別的な発言をされることがあるということです。誰にも言えない病気にかかり、やっとの思いで病院に行っているのに、その病院で医者や看護師から差別的な発言をされることも少なくないのです。「不潔なことをするからそんなことになるんだ」とか「君みたいな女がいるから世の中の性病はなくならないんだ」とか、そんなことを言われることもあるのです。
私が実際にある女性から聞いた話を紹介しましょう。その女性は、私の知人の知人で、あるとき数人で食事をしていたときに、たまたま席が横になったので話すことになりました。当時私は医学部の学生で、まだ臨床医学をほとんど知らない頃でした。話の流れで自分は医学部生だという話題になったときに、彼女は私にだけ聞こえるように身の上話を始めました。
彼女は数年前に、ある風俗店で働いていたというのです。風俗店で働くということは、言うまでもなく、様々な性感染のリスクがあります。特に症状が出たわけでもないのですが、性感染が心配になった彼女は、いくつかのクリニックを受診したそうです。
彼女は、医師や看護婦には、「なぜ受診したか」ということを正直に話しました。彼女は、現在の仕事のことも話しました。社会的には何かと差別の対象になる仕事ですが、医療従事者ならそのまま受け止めてくれて相談にのってくれると考えたのです。
ところが、彼女がかかったクリニックの医療従事者は全員、冷淡な態度をとったというのです。
「そんな仕事をしているのが悪いのです。」「すぐに仕事をやめなさい。」
どこへ行ってもそのように言われて、なぜ仕事を続けなければならないかという点については、誰も聞いてくれなかったというのです。彼女にとって、性感染のことを真剣に相談できるのは医療機関をおいて他にはなかったのです。本当は彼女だって仕事のことは誰にも言いたくなかったのです。
それに、彼女は好き好んでそのような仕事をしているわけではないのです。彼女の場合、両親の残した巨額の借金を返済するために、仕方なく働いていたそうです。もちろんこれは本当のことかどうかは分かりませんが、少なくとも私が聞いた印象では、高収入が得られるからとか、嫌いな仕事じゃないから、とかそんな理由で働いていたとは思えませんでした。
性感染症、これほどまで差別の対象となる病気は他にないのではないでしょうか。誰にも言えずにひとりで悩まなくてはならず、さらに医療機関でさえも差別的な発言を受けるのです。
彼女は、なぜ言う必要のない過去の嫌な思いを私に話したのでしょうか。現在は借金を返済し終えており、忘れたいことをわざわざ話す必要などなかったはずです。
私はこのように考えました。「私も数年先には医師になる以上、性感染症の患者をみることがあるかもしれない。私には他の患者と同様、差別することなく診てほしい。」、彼女はそれを伝えたかったのではないかと思うのです。
私は、そのとき、彼女の連絡先どころか名前も聞きませんでした。今ではどこにいるのかも分かりません。これから会うこともないでしょう。
けれども、私はこのことを語っているときの彼女の目を忘れることができません。そしてこのエピソードが、私が性感染症に取り組みたいと思った最大の理由なのです。
ちなみに性感染症を扱っている科というのは、まず性病科が筆頭にきますが、「性病科」の看板をあげているクリニックはほとんどありません。実際は、皮膚科、泌尿器科、婦人科などが、部分的にみているというのが現状です。
「部分的に」というのは、例えば、婦人科では男性はみませんし、皮膚科ではヘルペスやクラミジア、梅毒といった皮膚に症状の出る疾患は得意としますが、クラミジアや淋病といった疾患については通常みることはありません。これとは逆に、泌尿器科では、クラミジアや淋病以外の疾患はあまり得意としていません。
ところが、患者さんの立場にたったときに、これは相当不便です。というのは、まずひとつめに性感染というのは、重複感染していることが多いという問題があります。例えば、クラミジアとヘルペスに同時に感染したなどという場合、クラミジアは泌尿器科で、ヘルペスは皮膚科でというふうに、複数の医療機関を受診しなければならないのです。
もうひとつ、性感染は、パートナーを同時に治療しなければ意味がありません。勇気を出して、ふたりで婦人科に行っても、男性はみてくれないのです。
私は、あらゆる性感染症をパートナーも含めてトータルで治療していく必要があると考えています。
このような経緯があって、私は性感染症をトータルにみることのできる皮膚科医をめざそうと考えたわけです。