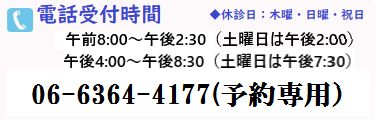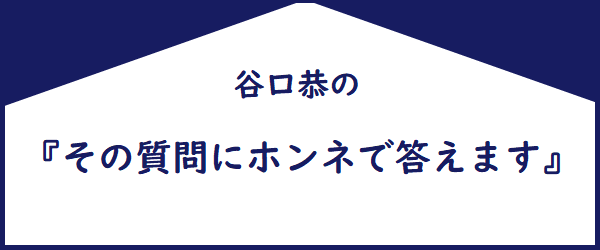メディカルエッセイ
37 人工呼吸器の是非 2006/4/15
最近、医師が人工呼吸器を止め、延命を中止したことに対する報道が注目を集めているようです。
2006年3月25日のasahi.comの報道によりますと、富山のある病院の外科医が、2000年から2005年にかけてかかわった末期の入院患者7人の人工呼吸器を外し、全員が死亡していたことが分かったそうです。この病院はこの医師の「延命治療の中止措置」について、倫理上問題があると判断し、院内調査委員会を設置するとともに、県警に届け出たとのことです。
この病院の院長によると、亡くなったのは同県内に住む50~90代の患者7人(男性4人、女性3人)で、いずれも意識がなく回復の見込みがない状態だったそうです。
そして、この外科医は病院側の調査に対し、人工呼吸器の取り外しについて「いずれも家族の同意を得ているが、うち1人は家族から本人の意思も確認できた」と説明し、病院によると、いずれも本人の同意書はないが、カルテには「家族の同意」を示す記述があるそうです。
こういう事件が報道されると、必ず「お前はどう思う?」と知人から聞かれます。「どう思う?」と聞かれて困るのは、症例というのはひとつひとつ異なるものであり、必ずしも一般論で論じることができないからです。
もう少し詳しくお話しましょう。
まず、個々の症例において、人工呼吸器をどのような状態で装着したかというのが重要になってきます。通常、末期の状態であれば、いずれ呼吸状態が悪化することが考えられ、その場合、気管内挿管をおこない人工呼吸器を用いた治療をおこなうかどうかというのを、あらかじめ本人もしくは家族と話をしておきます。
今回報道された事件では、末期の患者さんとされていますが、あらかじめそのような話をされていたのかどうかが明らかではありません。もしも、本人もしくは家族が「どんなことをしてでも少しでも延命してください」という希望を持たれていたのであれば、この外科医のとった行動は許されるべきではないということになります。
しかし、報道ではカルテに「家族の同意」があるとされています。とすると、人工呼吸器の話をするまでに、つまり予想よりも早く呼吸状態が悪化したのか、あるいは、その患者さんの病気による呼吸状態の悪化ではなく、例えば何らかの理由で窒息や薬物の副作用で呼吸が停止し、緊急処置として人工呼吸器を装着した可能性も考えなくてはなりません。さらに、その患者さんが本当に末期といえる状態であったのかどうかという点については報道からは皆目見当がつきません。こうなると推測の域を出ずに、私が医師としてコメントするのは不適切ということになります。
今回の事件のように、余命いくばくもないと思われる患者さんに装着されている人工呼吸器を停止させるのは、いわゆる「安楽死」ということになります。実は、この「安楽死」については明確な定義がありません。
便宜上よく引き合いに出されるのが、いわゆる「東海大安楽死事件」に対して、1995年に横浜地裁が述べた「安楽死の3要件」です。それらは、(1)回復の見込みがなく、死が避けられない末期状態にある、(2)治療行為の中止を求める患者の意思表示か家族による患者の意思の推定がある、(3)「自然の死」を迎えさせる目的に沿った決定である、の3つです。
人工呼吸器を装着すべきか否か、というのは可能であれば、できるだけ早い時期に本人もしくは家族に考えておいてもらうのがいい、というのが私の考えです。そのため、私はまだ患者さんの元気な早い時期に本人及び家族にこの話をしておくようにしています。「先生、そんなに早く結論ださないといけないんですか」、と聞かれることもありますが、いったん装着した人工呼吸器のスイッチを切るというのは、今回報道された事件のように合法かどうかという点がはっきりしませんし、正直に言って私自身に「スイッチを切る」という行為は抵抗があるのです。(念のために言っておくと、私は今回の外科医を非難しているわけではありません。私自身の臨床医としての、あるいはひとりの人間としての未熟性から、今の私には人工呼吸器を外すことに抵抗があるのです。)
人工呼吸器というのは、単なる延命医療の道具と考えている人もいるようですが、人工呼吸器がなければ助かる命が助からなくなることもあります。例えば健康な人が窒息や薬物中毒など急激に呼吸困難に陥ったような場合、迅速に気道を確保し、人工呼吸器を接続し、一時的に器械の力を借りて呼吸をおこなうことがあります。この場合、治療がうまく進めば、何事もなかったかのように復帰することができます。
また、全身麻酔の手術のときは人工呼吸器を接続し呼吸管理をおこなうことが必要です。人工呼吸器を用いた呼吸管理がおこなえるからこそ長時間の手術も安心しておこなうことができるのです。
つまるところ、「人工呼吸器の良し悪し」というのは単純な理屈で語られるべきものではなく、個々の症例でしっかりと検討されるべきものということになります。
末期の状態であれば、最近は人工呼吸器を用いた延命治療を望まない人が増えているというようなことが言われますが、そもそも生命についての決定権は本人(もしくは家族)にあるわけで、医療従事者が決めるべきものではありません。
したがって、例えば、脳死になったときに臓器を提供すべきかどうか、といった問題と同様、患者さんの意識がしっかりとしている早い段階で決めておくべきものだと私は思うのです。
最近経験した、末期癌の患者さんのことをお話したいと思います。
その患者さんは80代の男性で、病気は、ある消化器系の癌で、もはや手術ができないほど進行している状態でした。数ヶ月ももたないと思われたため、あらかじめ本人と家族に、呼吸状態が悪化したときに呼吸器をつけるかどうかを相談していました。本人及び家族の返事はNO! つまり、人工呼吸器をつけたところで寿命がそれほど変わるものでもなく、癌自体は治らないのだから、ここまでくれば自然なかたちにまかせたい、とのことでした。「この患者さんは死というものを完全に受け入れている」、それが私の印象でした。
よく晴れたある日曜日の午後、いつものように昼食を終えた患者さんの様態が少しずつ変化しだしました。血圧や呼吸数は正常なのですが、意識がぼーっとしてきています。「これは家族を呼んだ方がいい」、私はそう判断しました。
意識状態を正確に把握するために、痛みの刺激を与えてどのような反応をとるかをみることがあります。私は、患者さんを少したたいたりつねったりして刺激を与えてみましたが、表情はまったく変わりません。これは意識状態がかなり悪いことを示しているのですが、しかしながらその表情が非常に穏やかなのです。この患者さんは、癌の末期なのにもかかわらず日頃から痛みをほとんど訴えず、強力な鎮痛剤も使っていませんでした。そのうちに血圧が下がりだし、呼吸の回数が少なくなりだしました。
そして、ちょうど家族の方々が到着したのと同時に、静かに息をひきとりました。
私はこの患者さんの表情が今も忘れられません。癌の患者さんによくある苦悶の表情を見せることなく、まるで、「生命をまっとうしました」、と宣言しているような印象を私は持ちました。この患者さんは末期癌であったことは間違いありませんが、病気が直接の死因というよりも、むしろ自然なかたちで生命に終止符を打たれたのかもしれません。
もしも、この患者さんに人工呼吸器を装着していれば、このような表情は見られなかったに違いありません。人工呼吸器をつなぐということは、プラスチックの管を口(あるいは鼻)から気管に挿入します。そしてその管を固定するために、口の周りをテープで何重にもとめることになります。そして呼吸器の「シュー」という乾いた無機質な音が規則的に病室に響き渡ります。患者さんの心臓が弱ろうが呼吸器は同じリズムで空気を送ってきますから、末期の患者さんに接続した呼吸器はその患者さんをいじめているように見えることもあります。
私は、この患者さんは人工呼吸器を使わなくてよかったんじゃないかな、と思いました。
家族の前で死亡宣告を終えた後、この方の奥様が話されました。
「先生、主人の死に顔がこんなにも穏やかだとは思いませんでした。こんなに幸せそうな表情をしているなんて・・・・」
口にはしませんでしたが、私も同じことを感じていました。
2006年3月25日のasahi.comの報道によりますと、富山のある病院の外科医が、2000年から2005年にかけてかかわった末期の入院患者7人の人工呼吸器を外し、全員が死亡していたことが分かったそうです。この病院はこの医師の「延命治療の中止措置」について、倫理上問題があると判断し、院内調査委員会を設置するとともに、県警に届け出たとのことです。
この病院の院長によると、亡くなったのは同県内に住む50~90代の患者7人(男性4人、女性3人)で、いずれも意識がなく回復の見込みがない状態だったそうです。
そして、この外科医は病院側の調査に対し、人工呼吸器の取り外しについて「いずれも家族の同意を得ているが、うち1人は家族から本人の意思も確認できた」と説明し、病院によると、いずれも本人の同意書はないが、カルテには「家族の同意」を示す記述があるそうです。
こういう事件が報道されると、必ず「お前はどう思う?」と知人から聞かれます。「どう思う?」と聞かれて困るのは、症例というのはひとつひとつ異なるものであり、必ずしも一般論で論じることができないからです。
もう少し詳しくお話しましょう。
まず、個々の症例において、人工呼吸器をどのような状態で装着したかというのが重要になってきます。通常、末期の状態であれば、いずれ呼吸状態が悪化することが考えられ、その場合、気管内挿管をおこない人工呼吸器を用いた治療をおこなうかどうかというのを、あらかじめ本人もしくは家族と話をしておきます。
今回報道された事件では、末期の患者さんとされていますが、あらかじめそのような話をされていたのかどうかが明らかではありません。もしも、本人もしくは家族が「どんなことをしてでも少しでも延命してください」という希望を持たれていたのであれば、この外科医のとった行動は許されるべきではないということになります。
しかし、報道ではカルテに「家族の同意」があるとされています。とすると、人工呼吸器の話をするまでに、つまり予想よりも早く呼吸状態が悪化したのか、あるいは、その患者さんの病気による呼吸状態の悪化ではなく、例えば何らかの理由で窒息や薬物の副作用で呼吸が停止し、緊急処置として人工呼吸器を装着した可能性も考えなくてはなりません。さらに、その患者さんが本当に末期といえる状態であったのかどうかという点については報道からは皆目見当がつきません。こうなると推測の域を出ずに、私が医師としてコメントするのは不適切ということになります。
今回の事件のように、余命いくばくもないと思われる患者さんに装着されている人工呼吸器を停止させるのは、いわゆる「安楽死」ということになります。実は、この「安楽死」については明確な定義がありません。
便宜上よく引き合いに出されるのが、いわゆる「東海大安楽死事件」に対して、1995年に横浜地裁が述べた「安楽死の3要件」です。それらは、(1)回復の見込みがなく、死が避けられない末期状態にある、(2)治療行為の中止を求める患者の意思表示か家族による患者の意思の推定がある、(3)「自然の死」を迎えさせる目的に沿った決定である、の3つです。
人工呼吸器を装着すべきか否か、というのは可能であれば、できるだけ早い時期に本人もしくは家族に考えておいてもらうのがいい、というのが私の考えです。そのため、私はまだ患者さんの元気な早い時期に本人及び家族にこの話をしておくようにしています。「先生、そんなに早く結論ださないといけないんですか」、と聞かれることもありますが、いったん装着した人工呼吸器のスイッチを切るというのは、今回報道された事件のように合法かどうかという点がはっきりしませんし、正直に言って私自身に「スイッチを切る」という行為は抵抗があるのです。(念のために言っておくと、私は今回の外科医を非難しているわけではありません。私自身の臨床医としての、あるいはひとりの人間としての未熟性から、今の私には人工呼吸器を外すことに抵抗があるのです。)
人工呼吸器というのは、単なる延命医療の道具と考えている人もいるようですが、人工呼吸器がなければ助かる命が助からなくなることもあります。例えば健康な人が窒息や薬物中毒など急激に呼吸困難に陥ったような場合、迅速に気道を確保し、人工呼吸器を接続し、一時的に器械の力を借りて呼吸をおこなうことがあります。この場合、治療がうまく進めば、何事もなかったかのように復帰することができます。
また、全身麻酔の手術のときは人工呼吸器を接続し呼吸管理をおこなうことが必要です。人工呼吸器を用いた呼吸管理がおこなえるからこそ長時間の手術も安心しておこなうことができるのです。
つまるところ、「人工呼吸器の良し悪し」というのは単純な理屈で語られるべきものではなく、個々の症例でしっかりと検討されるべきものということになります。
末期の状態であれば、最近は人工呼吸器を用いた延命治療を望まない人が増えているというようなことが言われますが、そもそも生命についての決定権は本人(もしくは家族)にあるわけで、医療従事者が決めるべきものではありません。
したがって、例えば、脳死になったときに臓器を提供すべきかどうか、といった問題と同様、患者さんの意識がしっかりとしている早い段階で決めておくべきものだと私は思うのです。
最近経験した、末期癌の患者さんのことをお話したいと思います。
その患者さんは80代の男性で、病気は、ある消化器系の癌で、もはや手術ができないほど進行している状態でした。数ヶ月ももたないと思われたため、あらかじめ本人と家族に、呼吸状態が悪化したときに呼吸器をつけるかどうかを相談していました。本人及び家族の返事はNO! つまり、人工呼吸器をつけたところで寿命がそれほど変わるものでもなく、癌自体は治らないのだから、ここまでくれば自然なかたちにまかせたい、とのことでした。「この患者さんは死というものを完全に受け入れている」、それが私の印象でした。
よく晴れたある日曜日の午後、いつものように昼食を終えた患者さんの様態が少しずつ変化しだしました。血圧や呼吸数は正常なのですが、意識がぼーっとしてきています。「これは家族を呼んだ方がいい」、私はそう判断しました。
意識状態を正確に把握するために、痛みの刺激を与えてどのような反応をとるかをみることがあります。私は、患者さんを少したたいたりつねったりして刺激を与えてみましたが、表情はまったく変わりません。これは意識状態がかなり悪いことを示しているのですが、しかしながらその表情が非常に穏やかなのです。この患者さんは、癌の末期なのにもかかわらず日頃から痛みをほとんど訴えず、強力な鎮痛剤も使っていませんでした。そのうちに血圧が下がりだし、呼吸の回数が少なくなりだしました。
そして、ちょうど家族の方々が到着したのと同時に、静かに息をひきとりました。
私はこの患者さんの表情が今も忘れられません。癌の患者さんによくある苦悶の表情を見せることなく、まるで、「生命をまっとうしました」、と宣言しているような印象を私は持ちました。この患者さんは末期癌であったことは間違いありませんが、病気が直接の死因というよりも、むしろ自然なかたちで生命に終止符を打たれたのかもしれません。
もしも、この患者さんに人工呼吸器を装着していれば、このような表情は見られなかったに違いありません。人工呼吸器をつなぐということは、プラスチックの管を口(あるいは鼻)から気管に挿入します。そしてその管を固定するために、口の周りをテープで何重にもとめることになります。そして呼吸器の「シュー」という乾いた無機質な音が規則的に病室に響き渡ります。患者さんの心臓が弱ろうが呼吸器は同じリズムで空気を送ってきますから、末期の患者さんに接続した呼吸器はその患者さんをいじめているように見えることもあります。
私は、この患者さんは人工呼吸器を使わなくてよかったんじゃないかな、と思いました。
家族の前で死亡宣告を終えた後、この方の奥様が話されました。
「先生、主人の死に顔がこんなにも穏やかだとは思いませんでした。こんなに幸せそうな表情をしているなんて・・・・」
口にはしませんでしたが、私も同じことを感じていました。