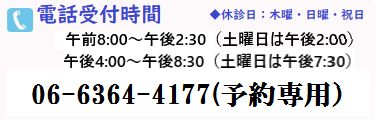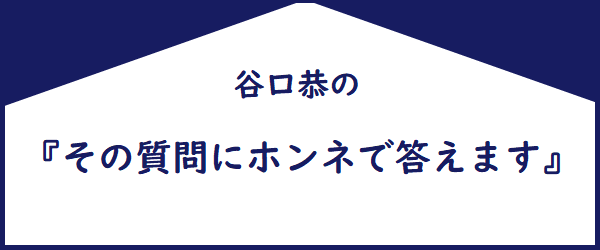メディカルエッセイ
51 ある同級生に感謝していること 2007/4/25
以前別のところにも書きましたが、私が医師になってまだ2ヶ月しかたっていない2002年の7月、大学病院の近くの路上で交通事故に会いました。
結局、その後27日間の入院生活を強いられることになったのですが、この入院生活は今思い出してもかなりの苦悩が伴うものでした。
激痛ではないものの鈍い痛みが首と右腕を常に支配し、どのように表現していいか分からない不快な頭重感、それに右腕のしびれや脱力感と共存しなければなりませんでした。右手にはほとんど力が入らずに、ペンや箸はなんとか持てるものの、少し重いドアを開けることすらままならない状態でした。
しかし、私を最も苦しめたのはそういった身体的な苦痛よりもむしろ精神的な閉塞感でした。なにしろ、医師になってまだ2ヶ月しかたっていない時の入院生活です。早く仕事を覚えなければならない時期なのにもかかわらず安静を強いられるのです。
医師の仕事を続けることはもうできないかもしれない・・・、そんな考えさえいつしか頭を支配するようになりました。特に辛いのが夜です。ほとんどの患者さんがそうであるように、私の痛みも日中よりも夜間に増強されます。少しでも痛みが軽減される姿勢を探すのに一晩中かかって、結局ほとんど眠れないという日もありました。強力な睡眠薬を使っても、不安感が薬の効能を打ち消します。
入院生活を通して何人かの友人・知人が見舞いに来てくれたことは心の支えになりましたが、単に挨拶に来ただけ、と明らかな社交辞令風の人もいて、そういうときはかえって精神状態が悪くなります。
一方で、私の立場に立って話を聞いてくれるような人たちもいて入院生活の励みになりました。今回は、そんな心優しい人たちのなかでも私が最も印象に残っているひとりの女性について思い出してみたいと思います。
その女性は私の医学部の同級生です。私が医学部に入学したのは4年間のサラリーマン生活を終えた後の27歳のときですが、その女性は現役で入学していますから私とは9歳年が離れていることになります。
当時は医学部を卒業した後は卒業生の大半が大学病院で研修を受けていました。私もその同級生も大学を卒業し、そのまま大学病院で研修医生活を送っていました。
入院してちょうど1週間が過ぎようとしていたある夜にその同級生は私のベッドサイドにやってきました。それまでも他の同級生たちが何人かは見舞いに来てくれていましたが、仕事が忙しいこともあって、たいていは挨拶程度の話しかせずに数分で去っていきました。同じフロアで働く同級生さえも、それほど長い時間滞在せずに仕事に戻っていました。
1年目の研修医は寝る時間もないほどに忙しいものですから、短時間でもベッドサイドに来てくれることに感謝しなければならないのは分かるのですが、やはりひとりの患者としてみると少し寂しい気もします。
そんななか、その同級生はある晩突然やって来て、1時間以上も私のそばにいてくれたのです。私はその女性とは学生の頃から仲がよかったとは思いますが、例えばふたりで食事にいくような関係ではありません。おそらくふたりでじっくり話をしたことなどそれまではなかったと思います。
けれども、そのときその同級生は、どこからか椅子をもってきてベッドに横たわっている私の横に座り、ゆっくりと私の話を聞いてくれたのです。
私はどちらかと言うと、自分が話すよりも相手の話を聞くことの方が多いのですが、そのときは、彼女の話を聞くのではなく、一方的に私が話しをしていることに会話の途中で気づいたのを今でも覚えています。
しかも、私の話していたことは他愛もないことばかりで、彼女にとって興味深い話はほとんどなかったと思います。それでも彼女は、ときには相槌を打ち、ときには笑顔を浮かべ、ときには私の気持ちが分かると言い、私の話に付き合ってくれたのです。
気がつくと1時間以上も経過していました。私は、彼女が仕事を途中で中断して見舞いに来てくれていることを思い出しました。おそらく、彼女はこれからカルテの整理やレポートの作成などで少なくとも数時間は病院に残らなければならないはずです。私は、大変申し訳ない気持ちに駆られましたが、あえて謝りの言葉は述べず、代わりにお礼を言って彼女の背中を見送りました。
彼女が去ってからも、心の重荷がすーっとおりて身体が軽くなったような感じが続いていました。前日まで強力な睡眠薬を倍量飲んでも寝られなかったのが、その日は担当の看護師が睡眠薬を持ってくる前に深い眠りに落ちていました。
薬よりも手術よりも優れた治療法・・・、とまでは言えないでしょうが、「患者のそばでじっくりと患者の話を聞く」というのは、患者さんの精神状態を安定させるだけでなく、身体的苦痛を取り除くことさえあるということが、ひとりの同級生のおかげで分かりました。
実際の臨床の現場では、ひとりの患者さんに時間を取り過ぎることが許されないケースが多々あります。他の患者さんを待たせることになりますし、病院やクリニックの経営的な観点からは非効率だからです。
しかしながら、ときに医師が患者に共感すること(これを「ラポール」と言います)が既存のどんな治療法よりも優れていることがあるということは、医療者はもっと注目すべきではないかと私は考えています。
これを書いている今、あのとき見舞いに来てくれたあの同級生とはもう5年近くも会っていないことに気付きました。彼女がいま、どこの病院で働いているのかを私は知りませんが、きっと患者さんから大きな信頼を寄せられる医師になっているに違いありません。
結局、その後27日間の入院生活を強いられることになったのですが、この入院生活は今思い出してもかなりの苦悩が伴うものでした。
激痛ではないものの鈍い痛みが首と右腕を常に支配し、どのように表現していいか分からない不快な頭重感、それに右腕のしびれや脱力感と共存しなければなりませんでした。右手にはほとんど力が入らずに、ペンや箸はなんとか持てるものの、少し重いドアを開けることすらままならない状態でした。
しかし、私を最も苦しめたのはそういった身体的な苦痛よりもむしろ精神的な閉塞感でした。なにしろ、医師になってまだ2ヶ月しかたっていない時の入院生活です。早く仕事を覚えなければならない時期なのにもかかわらず安静を強いられるのです。
医師の仕事を続けることはもうできないかもしれない・・・、そんな考えさえいつしか頭を支配するようになりました。特に辛いのが夜です。ほとんどの患者さんがそうであるように、私の痛みも日中よりも夜間に増強されます。少しでも痛みが軽減される姿勢を探すのに一晩中かかって、結局ほとんど眠れないという日もありました。強力な睡眠薬を使っても、不安感が薬の効能を打ち消します。
入院生活を通して何人かの友人・知人が見舞いに来てくれたことは心の支えになりましたが、単に挨拶に来ただけ、と明らかな社交辞令風の人もいて、そういうときはかえって精神状態が悪くなります。
一方で、私の立場に立って話を聞いてくれるような人たちもいて入院生活の励みになりました。今回は、そんな心優しい人たちのなかでも私が最も印象に残っているひとりの女性について思い出してみたいと思います。
その女性は私の医学部の同級生です。私が医学部に入学したのは4年間のサラリーマン生活を終えた後の27歳のときですが、その女性は現役で入学していますから私とは9歳年が離れていることになります。
当時は医学部を卒業した後は卒業生の大半が大学病院で研修を受けていました。私もその同級生も大学を卒業し、そのまま大学病院で研修医生活を送っていました。
入院してちょうど1週間が過ぎようとしていたある夜にその同級生は私のベッドサイドにやってきました。それまでも他の同級生たちが何人かは見舞いに来てくれていましたが、仕事が忙しいこともあって、たいていは挨拶程度の話しかせずに数分で去っていきました。同じフロアで働く同級生さえも、それほど長い時間滞在せずに仕事に戻っていました。
1年目の研修医は寝る時間もないほどに忙しいものですから、短時間でもベッドサイドに来てくれることに感謝しなければならないのは分かるのですが、やはりひとりの患者としてみると少し寂しい気もします。
そんななか、その同級生はある晩突然やって来て、1時間以上も私のそばにいてくれたのです。私はその女性とは学生の頃から仲がよかったとは思いますが、例えばふたりで食事にいくような関係ではありません。おそらくふたりでじっくり話をしたことなどそれまではなかったと思います。
けれども、そのときその同級生は、どこからか椅子をもってきてベッドに横たわっている私の横に座り、ゆっくりと私の話を聞いてくれたのです。
私はどちらかと言うと、自分が話すよりも相手の話を聞くことの方が多いのですが、そのときは、彼女の話を聞くのではなく、一方的に私が話しをしていることに会話の途中で気づいたのを今でも覚えています。
しかも、私の話していたことは他愛もないことばかりで、彼女にとって興味深い話はほとんどなかったと思います。それでも彼女は、ときには相槌を打ち、ときには笑顔を浮かべ、ときには私の気持ちが分かると言い、私の話に付き合ってくれたのです。
気がつくと1時間以上も経過していました。私は、彼女が仕事を途中で中断して見舞いに来てくれていることを思い出しました。おそらく、彼女はこれからカルテの整理やレポートの作成などで少なくとも数時間は病院に残らなければならないはずです。私は、大変申し訳ない気持ちに駆られましたが、あえて謝りの言葉は述べず、代わりにお礼を言って彼女の背中を見送りました。
彼女が去ってからも、心の重荷がすーっとおりて身体が軽くなったような感じが続いていました。前日まで強力な睡眠薬を倍量飲んでも寝られなかったのが、その日は担当の看護師が睡眠薬を持ってくる前に深い眠りに落ちていました。
薬よりも手術よりも優れた治療法・・・、とまでは言えないでしょうが、「患者のそばでじっくりと患者の話を聞く」というのは、患者さんの精神状態を安定させるだけでなく、身体的苦痛を取り除くことさえあるということが、ひとりの同級生のおかげで分かりました。
実際の臨床の現場では、ひとりの患者さんに時間を取り過ぎることが許されないケースが多々あります。他の患者さんを待たせることになりますし、病院やクリニックの経営的な観点からは非効率だからです。
しかしながら、ときに医師が患者に共感すること(これを「ラポール」と言います)が既存のどんな治療法よりも優れていることがあるということは、医療者はもっと注目すべきではないかと私は考えています。
これを書いている今、あのとき見舞いに来てくれたあの同級生とはもう5年近くも会っていないことに気付きました。彼女がいま、どこの病院で働いているのかを私は知りませんが、きっと患者さんから大きな信頼を寄せられる医師になっているに違いありません。