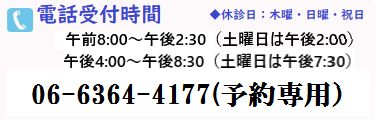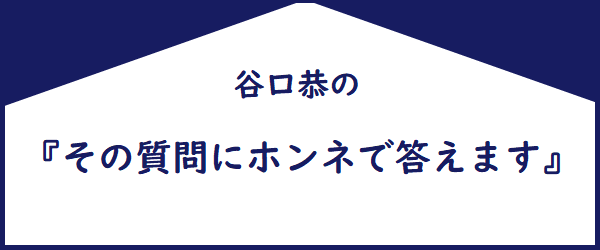マンスリーレポート
2015年4月号 「医療否定本」はなぜ問題か(前編)
ここ数年でいわゆる「医療否定本」という言葉を頻繁に聞くようになってきました。現代医療を否定する本は以前からありますが、一昔前までは、宗教者が書いたものであったり、自社製品を売りたいがために健康食品の会社が出版したものであったりと、そういうものが大半だったのですが、ここ数年は医師による医療否定本がブームになっています。
なかでも、元・慶應義塾大学医学部講師の近藤誠先生の『医者に殺されない47の心得』という本が飛び抜けて売れているそうです。最近、患者さんからも「どう思いますか」と聞かれることが増えてきたこともあり私も読んでみました。
近藤先生に批判的な意見が多いのは以前から知っていましたが、私自身は近藤先生の書籍は医学部の学生の頃に何冊か読んでおり、先生の残された功績は素晴らしいものと考えています。最も尊敬に値するのは、今では標準的治療とも呼べる乳癌に対する「乳房温存術」を日本で広められたことです。それまでは、ハルステッド法といって乳房のみならず大胸筋までごっそりと取ってしまう手術が主流だったのです。乳房温存術では可能な限り取り除く部位を最小限にするために、術後、胸のかたちに悩まされることがなくなるのです。
また、異論はあるものの近藤先生の「がんもどき」という考え方は興味深いものです。これは、ガンには2種類あり、ひとつは「本物のガン」、もうひとつがにせもののガン、つまり「がんもどき」という考えです。本物のガンは検診では発見することができず発見されたときには助かる術がない。だから何もすべきでない。一方、「がんもどき」は悪化しないからもともと何もする必要がない、とするものです。ここからガン検診は不要でありすべてのガンは「放置」すべき、という理論に発展します。
すべてのガンは検診すべきでなく見つかっても放置すべき、などという理論に賛成するわけにはいきませんし、すべて「放置」するなら、以前は近藤先生自身が推奨されていた乳ガンに対する「乳房温存術」すらすべきでない、ということになり自身の主張が矛盾することになります。
ただ「がんもどき」という考えがまったく間違いかというとそうではなく、ひとつ例をあげれば、私は甲状腺ガンの大半が「がんもどき」ではないかと思っています。甲状腺ガンの発症世界一は韓国で、1999年には年間2,866人しか診断されなかった甲状腺ガンが2013年にはなんと53,737人に診断がついています。この間でおよそ19倍も増加しているのです。現在韓国では人口10万人あたり97人が甲状腺癌の診断を受けていることになり、これはダントツで世界一位、世界平均の10倍以上になります。では、韓国で甲状腺ガンによる死亡数が減っているのかというと、これがまったく減っていないのです。
なぜ韓国でこれだけ甲状腺ガンがみつかるかというと、超音波検査を健康診断でほぼ全員に実施するようになったからです。余計な検査をしたせいで「がんもどき」が見つかり、見つかれば手術で甲状腺を摘出することになります。おまけに手術をするとその後は一生涯甲状腺ホルモンを飲み続けなければなりません。患者さんの負担は相当なものになりますし、医療費を圧迫することにもなります。
しかし、甲状腺ガンによる死亡数が減っていないということは、助からないガンは助からないわけで、検診にも意味がないということになります。このことだけを取り上げると近藤先生の「がんもどき」理論は正しいように思えます。
では他のガンはどうなのでしょうか。近藤先生は「がんもどき」理論をすべてのガンに広げ「ガン検診は一切不要」と主張します。しかしこれはあまりにも極論です。ひとつ例をあげると子宮頚ガンは定期的に検診をおこなうとほぼ100%早期発見が可能です。もしも「放置」をすると早期発見の機会が失われ助かる命が助からなくなります。
子宮頚ガンは比較的多いガンで有名人が罹患したことがしばしば報道されます。最近ではシーナ&ロケッツのシーナさんが、発見が遅れたために61歳で死亡されました。ZARDのヴォーカリストであった坂井泉水さんは、直接の死因は階段からの転落死ですが、子宮頚ガンの発見が遅れ肺に転移も認められていたことが報道されています。ガンの肺転移が見つかっていたということは、この不幸な転落事故がなかったとしても命は長くなかったことが予想されます。
我々医療者がこのような報道を聞くと、「有名人でなかなか検診を受ける機会がなかったのだろうが、検査を受けてさえいれば・・・」という気持ちを拭えません。しかし近藤先生は「二人の子宮頚ガンはがんもどきでなく本物のガンだったのだから検診を受けていても無駄だった」と言われるのでしょうか・・・。
子宮頚ガンは早期で発見できれば、円錐切除術といってごく一部を取り除く手術、もしくは放射線療法でも完全治癒が期待できます。(他にも治療方法がありますがここでの言及は避けます) しかしある程度発見が遅れると子宮をすべて摘出する必要があります。このタイミングを逃すと(坂井泉水さんのように)肺など他臓器に転移し助からなくなります。
ガンの発見が遅れたものの、子宮全摘をすることによって命が助かり現在も活躍されている有名人に森昌子さんがいます。現在は政治家の三原じゅん子さんも子宮頚ガンで子宮全摘をされています。近藤先生はこの二人に対しても「今生きているということはがんもどきだったのだから子宮を取るべきではなかった」と言われるのでしょうか・・・。
私が医学部の学生の頃に読んでいた近藤先生の著作はガンに関するものばかりだったのですが、『医者に殺されない47の心得』には他の疾患についても意見を述べられており、これらには同意できるものもあるのですが、問題だと言わざるを得ないものも目立ちます。
例えば同書のなかで「インフルエンザワクチンを打ってはいけない」と断言されています。結論から言えばこれは間違いでインフルエンザのワクチンは有用です。ただ、ワクチンに対していろんな意見があってもいいとは思いますし、それを自身の本で主張することは「表現の自由」だと思います。(私自身も子宮頚ガンのワクチンを定期化して中学1年生の女子全員に接種するという考えには反対です) ただし、近藤先生が言っているその理屈が卑怯であり、故意に読者をミスリードしようとする意図が感じられます。
インフルエンザワクチンを打ってはいけないその理由として、近藤先生は「WHO(世界保健機関)も厚生労働省も、ホームページ上で、インフルエンザワクチンで、感染を抑える働きは保証されていない、と表明しています」と書いています。これだけを読めば、WHOも厚労省も「推薦していない」ワクチンをすすめる医療機関は悪徳商法ではないのか!と読者をミスリードすることになりかねません。
この書き方が卑怯なのは、あたかもWHOや厚労省がインフルエンザワクチンをすすめていないような表現をとっていることです。実際は、もちろんWHOも厚労省もインフルエンザワクチンが重要であることを訴えています。感染抑制効果については年により異なり、たしかに2014年終わりから2015年の初めにかけて流行したインフルエンザにはワクチンの発症抑制効果は期待はずれでした。これはWHOがこのシーズンに流行ると予想していた型と別の型のウイルスが流行したためです。しかし、この場合でも重症化を防ぐことができ、他人への感染リスクを下げることができます。
仮に、重症化を防ぐことや他人への感染リスクを減少させる効果も期待していたほどではなかった、という新しい事実が将来判明したとしましょう。それでも、現在WHOも厚労省もインフルエンザワクチンを推薦しているのは事実であり、あたかもこの事実がないような誘導をするのは問題です。
もうひとつ例を挙げましょう。同書のなかで近藤先生は「ERCPで急性膵炎が生じることは決して少なくなく、本当に死亡する場合もあるのでおすすめできません」と書いています。ERCPというのは内視鏡的逆行性胆道膵管造影のことで、十二指腸まで内視鏡を入れて胆道と膵管の造影剤を注入する検査です。ERCPは急性膵炎が生じることがあり、死亡例があるのも事実です。ここまでは間違ったことは言っていません。しかし、この箇所を素直に読むと「胆管と膵臓の検査自体が無用だから受けるべきではなかった」と解釈できます。
現在は胆管や膵臓の検査にはERCPではなくMRCPを用います。MRCPであれば急性膵炎が起こらずに安全に検査ができるからです。MRCPをあえて避けてERCPを実施することなどほとんどないはずです。そして近藤先生はそれを知らないはずがありません。MRCPの存在を知っていてERCPの危険性だけを主張するのは悪意あるミスリードではないでしょうか。
医師が書く「医療否定本」で最も問題だと思うことを今回述べる予定でしたが、近藤誠先生の『医者に殺されない47の心得』の批判で予定の文字数を越えてしまいました。次回はその「最も問題なこと」について述べたいと思います。
参考:
『患者よ、がんと闘うな』文春文庫
『医者に殺されない47の心得 医療と薬を遠ざけて、元気に、長生きする方法』アスコム
『「治るがん」と「治らないがん」 医者が隠している「がん治療」の現実』講談社+α文庫
『よくない治療、ダメな医者から逃れるヒント』講談社+α文庫
なかでも、元・慶應義塾大学医学部講師の近藤誠先生の『医者に殺されない47の心得』という本が飛び抜けて売れているそうです。最近、患者さんからも「どう思いますか」と聞かれることが増えてきたこともあり私も読んでみました。
近藤先生に批判的な意見が多いのは以前から知っていましたが、私自身は近藤先生の書籍は医学部の学生の頃に何冊か読んでおり、先生の残された功績は素晴らしいものと考えています。最も尊敬に値するのは、今では標準的治療とも呼べる乳癌に対する「乳房温存術」を日本で広められたことです。それまでは、ハルステッド法といって乳房のみならず大胸筋までごっそりと取ってしまう手術が主流だったのです。乳房温存術では可能な限り取り除く部位を最小限にするために、術後、胸のかたちに悩まされることがなくなるのです。
また、異論はあるものの近藤先生の「がんもどき」という考え方は興味深いものです。これは、ガンには2種類あり、ひとつは「本物のガン」、もうひとつがにせもののガン、つまり「がんもどき」という考えです。本物のガンは検診では発見することができず発見されたときには助かる術がない。だから何もすべきでない。一方、「がんもどき」は悪化しないからもともと何もする必要がない、とするものです。ここからガン検診は不要でありすべてのガンは「放置」すべき、という理論に発展します。
すべてのガンは検診すべきでなく見つかっても放置すべき、などという理論に賛成するわけにはいきませんし、すべて「放置」するなら、以前は近藤先生自身が推奨されていた乳ガンに対する「乳房温存術」すらすべきでない、ということになり自身の主張が矛盾することになります。
ただ「がんもどき」という考えがまったく間違いかというとそうではなく、ひとつ例をあげれば、私は甲状腺ガンの大半が「がんもどき」ではないかと思っています。甲状腺ガンの発症世界一は韓国で、1999年には年間2,866人しか診断されなかった甲状腺ガンが2013年にはなんと53,737人に診断がついています。この間でおよそ19倍も増加しているのです。現在韓国では人口10万人あたり97人が甲状腺癌の診断を受けていることになり、これはダントツで世界一位、世界平均の10倍以上になります。では、韓国で甲状腺ガンによる死亡数が減っているのかというと、これがまったく減っていないのです。
なぜ韓国でこれだけ甲状腺ガンがみつかるかというと、超音波検査を健康診断でほぼ全員に実施するようになったからです。余計な検査をしたせいで「がんもどき」が見つかり、見つかれば手術で甲状腺を摘出することになります。おまけに手術をするとその後は一生涯甲状腺ホルモンを飲み続けなければなりません。患者さんの負担は相当なものになりますし、医療費を圧迫することにもなります。
しかし、甲状腺ガンによる死亡数が減っていないということは、助からないガンは助からないわけで、検診にも意味がないということになります。このことだけを取り上げると近藤先生の「がんもどき」理論は正しいように思えます。
では他のガンはどうなのでしょうか。近藤先生は「がんもどき」理論をすべてのガンに広げ「ガン検診は一切不要」と主張します。しかしこれはあまりにも極論です。ひとつ例をあげると子宮頚ガンは定期的に検診をおこなうとほぼ100%早期発見が可能です。もしも「放置」をすると早期発見の機会が失われ助かる命が助からなくなります。
子宮頚ガンは比較的多いガンで有名人が罹患したことがしばしば報道されます。最近ではシーナ&ロケッツのシーナさんが、発見が遅れたために61歳で死亡されました。ZARDのヴォーカリストであった坂井泉水さんは、直接の死因は階段からの転落死ですが、子宮頚ガンの発見が遅れ肺に転移も認められていたことが報道されています。ガンの肺転移が見つかっていたということは、この不幸な転落事故がなかったとしても命は長くなかったことが予想されます。
我々医療者がこのような報道を聞くと、「有名人でなかなか検診を受ける機会がなかったのだろうが、検査を受けてさえいれば・・・」という気持ちを拭えません。しかし近藤先生は「二人の子宮頚ガンはがんもどきでなく本物のガンだったのだから検診を受けていても無駄だった」と言われるのでしょうか・・・。
子宮頚ガンは早期で発見できれば、円錐切除術といってごく一部を取り除く手術、もしくは放射線療法でも完全治癒が期待できます。(他にも治療方法がありますがここでの言及は避けます) しかしある程度発見が遅れると子宮をすべて摘出する必要があります。このタイミングを逃すと(坂井泉水さんのように)肺など他臓器に転移し助からなくなります。
ガンの発見が遅れたものの、子宮全摘をすることによって命が助かり現在も活躍されている有名人に森昌子さんがいます。現在は政治家の三原じゅん子さんも子宮頚ガンで子宮全摘をされています。近藤先生はこの二人に対しても「今生きているということはがんもどきだったのだから子宮を取るべきではなかった」と言われるのでしょうか・・・。
私が医学部の学生の頃に読んでいた近藤先生の著作はガンに関するものばかりだったのですが、『医者に殺されない47の心得』には他の疾患についても意見を述べられており、これらには同意できるものもあるのですが、問題だと言わざるを得ないものも目立ちます。
例えば同書のなかで「インフルエンザワクチンを打ってはいけない」と断言されています。結論から言えばこれは間違いでインフルエンザのワクチンは有用です。ただ、ワクチンに対していろんな意見があってもいいとは思いますし、それを自身の本で主張することは「表現の自由」だと思います。(私自身も子宮頚ガンのワクチンを定期化して中学1年生の女子全員に接種するという考えには反対です) ただし、近藤先生が言っているその理屈が卑怯であり、故意に読者をミスリードしようとする意図が感じられます。
インフルエンザワクチンを打ってはいけないその理由として、近藤先生は「WHO(世界保健機関)も厚生労働省も、ホームページ上で、インフルエンザワクチンで、感染を抑える働きは保証されていない、と表明しています」と書いています。これだけを読めば、WHOも厚労省も「推薦していない」ワクチンをすすめる医療機関は悪徳商法ではないのか!と読者をミスリードすることになりかねません。
この書き方が卑怯なのは、あたかもWHOや厚労省がインフルエンザワクチンをすすめていないような表現をとっていることです。実際は、もちろんWHOも厚労省もインフルエンザワクチンが重要であることを訴えています。感染抑制効果については年により異なり、たしかに2014年終わりから2015年の初めにかけて流行したインフルエンザにはワクチンの発症抑制効果は期待はずれでした。これはWHOがこのシーズンに流行ると予想していた型と別の型のウイルスが流行したためです。しかし、この場合でも重症化を防ぐことができ、他人への感染リスクを下げることができます。
仮に、重症化を防ぐことや他人への感染リスクを減少させる効果も期待していたほどではなかった、という新しい事実が将来判明したとしましょう。それでも、現在WHOも厚労省もインフルエンザワクチンを推薦しているのは事実であり、あたかもこの事実がないような誘導をするのは問題です。
もうひとつ例を挙げましょう。同書のなかで近藤先生は「ERCPで急性膵炎が生じることは決して少なくなく、本当に死亡する場合もあるのでおすすめできません」と書いています。ERCPというのは内視鏡的逆行性胆道膵管造影のことで、十二指腸まで内視鏡を入れて胆道と膵管の造影剤を注入する検査です。ERCPは急性膵炎が生じることがあり、死亡例があるのも事実です。ここまでは間違ったことは言っていません。しかし、この箇所を素直に読むと「胆管と膵臓の検査自体が無用だから受けるべきではなかった」と解釈できます。
現在は胆管や膵臓の検査にはERCPではなくMRCPを用います。MRCPであれば急性膵炎が起こらずに安全に検査ができるからです。MRCPをあえて避けてERCPを実施することなどほとんどないはずです。そして近藤先生はそれを知らないはずがありません。MRCPの存在を知っていてERCPの危険性だけを主張するのは悪意あるミスリードではないでしょうか。
医師が書く「医療否定本」で最も問題だと思うことを今回述べる予定でしたが、近藤誠先生の『医者に殺されない47の心得』の批判で予定の文字数を越えてしまいました。次回はその「最も問題なこと」について述べたいと思います。
参考:
『患者よ、がんと闘うな』文春文庫
『医者に殺されない47の心得 医療と薬を遠ざけて、元気に、長生きする方法』アスコム
『「治るがん」と「治らないがん」 医者が隠している「がん治療」の現実』講談社+α文庫
『よくない治療、ダメな医者から逃れるヒント』講談社+α文庫