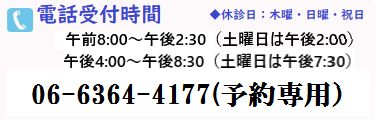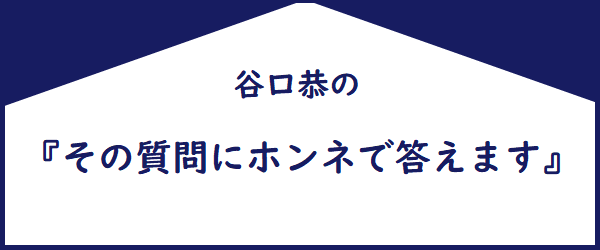マンスリーレポート
2019年2月 身体の底から湧き出てくる抑えがたい感情
医学部入学時には医師になるつもりのなかった私が、少しずつ医師への道を考え出したきっかけのひとつが病気で困っている人たちからの声を聞き始めたことでした。
「医師になる気はない」と事あるごとに言っていても、世間はそうはみなしません。そして世間の人からは医師も医学生も変わりがないと思われるのでしょう。医学部入学当初から、知り合いの知り合いといった人たちから「病気の相談に乗ってほしい」という依頼がよく来ました。
まだ医学を学び始めたばかりの者にそんな相談をされてもまともな答えができるはずがありません。まして私は「医師になる気はない」と言っているのです。「知り合いの知り合い」ですから会ったこともない人たちであり、無責任なことは言えませんからやんわりと断るようにしていました。ですが、知り合い(必ずしも親しいわけではない)から「話だけでも聞いてやってほしい」としつこく言われ、渋々と話を聞くという機会が何度かありました。
彼(女)らは口をそろえて「医者はまともに話を聞いてくれない」と言います。医学部で実習が始まるのは5回生からで、このとき私はまだ臨床の現場をほとんど知りません。初めて会う人たちから医師の悪口を聞かされてもどうしていいか分かりません。そもそも他人を悪くいう話を聞くときは、できるだけ客観的な立場に立ち、相手(この場合は医療者)からも話を聞くべきです。ですが、そういったことを差し引いたとしても私には彼(女)らの気持ちが分かるような気がしました。もう少し正確に言うと「医者側にも言い分があるだろうが、受診してこのような絶望的な気持ちになってしまっている人がいることをきちんと受け止めなければならない」と感じたのです。
仏語の勉強で挫折し、実験にセンスがないことを認めざるを得なくなり、入学時に考えていた研究の道を諦めかけていたところに、こういった話を頻繁に聞くようになり、私の心は次第に臨床へと傾いていきました(参考:マンスリーレポート2017年8月「やりたい仕事」よりも重要なこと~後編~)。自分が医師になったなら患者さんにこういう気持ちを持たせたくない、と考えるようになったのです。
そのうち私はあることに気づきました。私に「医者はまともに話を聞いてくれない」と言うとき、本当に言いたいことは医師の傲慢さや非人間性についてではなく、「医療者から見放されればどうしていいか分からない...」という"絶望感"だということに。そして、「いかなる人にもこの"絶望感"を持たせてはいけない」と思ったのです。
その後私は医療者や医療機関に不満をもつ多くの人と話す機会を持ちました。いわゆる「たらい回し」をされた人、セクシャルマイノリティであることを知られて差別的な言葉を言われたという人、セックスワークをしていることを思い切って医師に話すとひどいことを言われたという人、民間療法の話をすると医師にキレられたという人...。医師になってからはHIV陽性の人から話を聞く機会も増えてきました。医療者や医療機関に不満をもつ彼(女)らはたしかに軽症例も多いのですが、受診が必要、少なくとも医療者からの適切な助言が必要な人たちです。
こういった人たちのことを考えると、身体の奥から「抑えられない感情」が湧き出てきます。この感情は奥底からジワジワと湧き出てくるもので、私の身体を支配し、ときに思考を停止させます。病気の人を放っておいてはいけないというのは正しいことですが、正しいから実践するのではなく、私にとってはこの感情が文字通り「抑えられない」が故に行動せざるを得ないのです。初めてタイのエイズ施設を訪問し、他の医療機関で門前払いをされたという患者さんの話を聞いたときには抑制できない"怒り"がこみ上げてきました。
太融寺町谷口医院(以下「谷口医院」)には「他の医療機関で診てもらえなかった」といって何軒も渡り歩いてようやくたどり着いた、という患者さんが少なくありません。そういった症例は軽症である場合も多く、そもそも医療機関受診が客観的には不要というケースも多いのですが、そうでない場合もときにあります。
そのような「他院で診てもらえなかった」という症例で、数年前から増加しているのが「外国人」です。
外国人の患者さんの多くは、たとえ日本語か英語ができたとしてもそれなりに時間がかかります。また、英語は医師なら少なくとも読み書きはできますが、受付スタッフや看護師となるとコミュニケーションをとるのが困難という場合も少なくありません。これは大きな病院でも(というより、大きな病院の方が)融通が利かず、患者さんが電話しても話が通じず切られ、直接受診しても追い返され、ということがしばしばあります。
谷口医院を受診するまでにすでに5、6軒の医療機関を受診したという外国人も珍しくありません。こういう話を聞くと身体の奥から湧き出てくる感情が抑えられなくなってくるのです。医療は平等、とかそういったきれいごとを言いたいわけではありません。理屈の上で正しいからといった正論を述べたいわけでもありません。そのような理想を語りたいのではなく、もっと根源的で個人的な「感情」に抗うことができないのです。
海外で困った事態となったときや、突然の病気や怪我が起こったときに、現地の人たちに優しくしてもらった経験がある人は少なくないでしょう。キリスト教では聖書の「ヘブル人への手紙」のなかで「旅人をもてなすことを忘れてはならない」と書かれています(参考:「ヘブル人への手紙」)。イスラム教ではコーランの中に「旅人を助けよ」という教えがあると聞きます。仏教では私の知る限り「旅人」という言葉は見当たりませんが「利他」が基本的な教えであることは言うまでもありません(注1)。
日本に興味がありはるばる異国の地からやってきて、そこで予期せぬ病気に罹患してしまった。こんなとき、我々日本人はその外国人を助ける義務があると言えば言い過ぎでしょうか。谷口医院のミッション・ステイトメント第3条は「年齢・性別(sex,gender)・国籍・宗教・職業などに関わらず全ての受診者に対し平等に接する」です。逆差別もしないことを原則としていますが、複数の医療機関でイヤな思いをしてきたという外国人には少々優先的に働きかけるべきではないかとさえ最近は思っています。
ですから、メールでの問い合わせがあったとき、(内容にもよりますが)英語での外国人からの問い合わせを優先して返答するようにしています(もちろん日本人の患者さんからのメールもルール通り翌朝には返信しています)。谷口医院は総合診療のクリニックですから小児から高齢者までたいていの疾患は治療しており外国人の場合も95%は谷口医院で完結させるか、または帰国直後に母国の医療機関を受診できるように紹介状を作成します。ですが、残りの5%は日本国内での入院や専門医の治療が必要となり、このときに紹介先が見つからずに苦労することが多々あります。
そのようないきさつから、昨年(2018年)7月に「関西の外国人医療を考える会」という任意団体を立ち上げました。先日(2019年1月27日)は第2回の集会を開いて外国人医療に関心のある医療者と意見交換をおこないました。来阪する外国人は増加し続けているのにもかかわらず英語で対応してくれる医療者や医療機関が今もとても少ないのです。
残された医師としての時間のなかで、外国人が医療を受けるのに苦労しない社会を必ずつくる! これが現在の私が最も力をいれているミッションのひとつです。
************
注1:『大乗起信論』(岩波文庫)によれば、「五門」の第一の布施門のなかに次のような記載があります。
「もし人が厄難に遭い、恐怖し、また、危険が切迫しているのを見た場合には、己れに可能な(堪任)度合に応じて、その人に無畏を与えよ」
「医師になる気はない」と事あるごとに言っていても、世間はそうはみなしません。そして世間の人からは医師も医学生も変わりがないと思われるのでしょう。医学部入学当初から、知り合いの知り合いといった人たちから「病気の相談に乗ってほしい」という依頼がよく来ました。
まだ医学を学び始めたばかりの者にそんな相談をされてもまともな答えができるはずがありません。まして私は「医師になる気はない」と言っているのです。「知り合いの知り合い」ですから会ったこともない人たちであり、無責任なことは言えませんからやんわりと断るようにしていました。ですが、知り合い(必ずしも親しいわけではない)から「話だけでも聞いてやってほしい」としつこく言われ、渋々と話を聞くという機会が何度かありました。
彼(女)らは口をそろえて「医者はまともに話を聞いてくれない」と言います。医学部で実習が始まるのは5回生からで、このとき私はまだ臨床の現場をほとんど知りません。初めて会う人たちから医師の悪口を聞かされてもどうしていいか分かりません。そもそも他人を悪くいう話を聞くときは、できるだけ客観的な立場に立ち、相手(この場合は医療者)からも話を聞くべきです。ですが、そういったことを差し引いたとしても私には彼(女)らの気持ちが分かるような気がしました。もう少し正確に言うと「医者側にも言い分があるだろうが、受診してこのような絶望的な気持ちになってしまっている人がいることをきちんと受け止めなければならない」と感じたのです。
仏語の勉強で挫折し、実験にセンスがないことを認めざるを得なくなり、入学時に考えていた研究の道を諦めかけていたところに、こういった話を頻繁に聞くようになり、私の心は次第に臨床へと傾いていきました(参考:マンスリーレポート2017年8月「やりたい仕事」よりも重要なこと~後編~)。自分が医師になったなら患者さんにこういう気持ちを持たせたくない、と考えるようになったのです。
そのうち私はあることに気づきました。私に「医者はまともに話を聞いてくれない」と言うとき、本当に言いたいことは医師の傲慢さや非人間性についてではなく、「医療者から見放されればどうしていいか分からない...」という"絶望感"だということに。そして、「いかなる人にもこの"絶望感"を持たせてはいけない」と思ったのです。
その後私は医療者や医療機関に不満をもつ多くの人と話す機会を持ちました。いわゆる「たらい回し」をされた人、セクシャルマイノリティであることを知られて差別的な言葉を言われたという人、セックスワークをしていることを思い切って医師に話すとひどいことを言われたという人、民間療法の話をすると医師にキレられたという人...。医師になってからはHIV陽性の人から話を聞く機会も増えてきました。医療者や医療機関に不満をもつ彼(女)らはたしかに軽症例も多いのですが、受診が必要、少なくとも医療者からの適切な助言が必要な人たちです。
こういった人たちのことを考えると、身体の奥から「抑えられない感情」が湧き出てきます。この感情は奥底からジワジワと湧き出てくるもので、私の身体を支配し、ときに思考を停止させます。病気の人を放っておいてはいけないというのは正しいことですが、正しいから実践するのではなく、私にとってはこの感情が文字通り「抑えられない」が故に行動せざるを得ないのです。初めてタイのエイズ施設を訪問し、他の医療機関で門前払いをされたという患者さんの話を聞いたときには抑制できない"怒り"がこみ上げてきました。
太融寺町谷口医院(以下「谷口医院」)には「他の医療機関で診てもらえなかった」といって何軒も渡り歩いてようやくたどり着いた、という患者さんが少なくありません。そういった症例は軽症である場合も多く、そもそも医療機関受診が客観的には不要というケースも多いのですが、そうでない場合もときにあります。
そのような「他院で診てもらえなかった」という症例で、数年前から増加しているのが「外国人」です。
外国人の患者さんの多くは、たとえ日本語か英語ができたとしてもそれなりに時間がかかります。また、英語は医師なら少なくとも読み書きはできますが、受付スタッフや看護師となるとコミュニケーションをとるのが困難という場合も少なくありません。これは大きな病院でも(というより、大きな病院の方が)融通が利かず、患者さんが電話しても話が通じず切られ、直接受診しても追い返され、ということがしばしばあります。
谷口医院を受診するまでにすでに5、6軒の医療機関を受診したという外国人も珍しくありません。こういう話を聞くと身体の奥から湧き出てくる感情が抑えられなくなってくるのです。医療は平等、とかそういったきれいごとを言いたいわけではありません。理屈の上で正しいからといった正論を述べたいわけでもありません。そのような理想を語りたいのではなく、もっと根源的で個人的な「感情」に抗うことができないのです。
海外で困った事態となったときや、突然の病気や怪我が起こったときに、現地の人たちに優しくしてもらった経験がある人は少なくないでしょう。キリスト教では聖書の「ヘブル人への手紙」のなかで「旅人をもてなすことを忘れてはならない」と書かれています(参考:「ヘブル人への手紙」)。イスラム教ではコーランの中に「旅人を助けよ」という教えがあると聞きます。仏教では私の知る限り「旅人」という言葉は見当たりませんが「利他」が基本的な教えであることは言うまでもありません(注1)。
日本に興味がありはるばる異国の地からやってきて、そこで予期せぬ病気に罹患してしまった。こんなとき、我々日本人はその外国人を助ける義務があると言えば言い過ぎでしょうか。谷口医院のミッション・ステイトメント第3条は「年齢・性別(sex,gender)・国籍・宗教・職業などに関わらず全ての受診者に対し平等に接する」です。逆差別もしないことを原則としていますが、複数の医療機関でイヤな思いをしてきたという外国人には少々優先的に働きかけるべきではないかとさえ最近は思っています。
ですから、メールでの問い合わせがあったとき、(内容にもよりますが)英語での外国人からの問い合わせを優先して返答するようにしています(もちろん日本人の患者さんからのメールもルール通り翌朝には返信しています)。谷口医院は総合診療のクリニックですから小児から高齢者までたいていの疾患は治療しており外国人の場合も95%は谷口医院で完結させるか、または帰国直後に母国の医療機関を受診できるように紹介状を作成します。ですが、残りの5%は日本国内での入院や専門医の治療が必要となり、このときに紹介先が見つからずに苦労することが多々あります。
そのようないきさつから、昨年(2018年)7月に「関西の外国人医療を考える会」という任意団体を立ち上げました。先日(2019年1月27日)は第2回の集会を開いて外国人医療に関心のある医療者と意見交換をおこないました。来阪する外国人は増加し続けているのにもかかわらず英語で対応してくれる医療者や医療機関が今もとても少ないのです。
残された医師としての時間のなかで、外国人が医療を受けるのに苦労しない社会を必ずつくる! これが現在の私が最も力をいれているミッションのひとつです。
************
注1:『大乗起信論』(岩波文庫)によれば、「五門」の第一の布施門のなかに次のような記載があります。
「もし人が厄難に遭い、恐怖し、また、危険が切迫しているのを見た場合には、己れに可能な(堪任)度合に応じて、その人に無畏を与えよ」