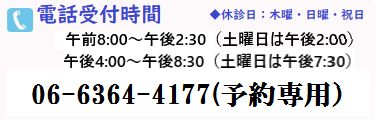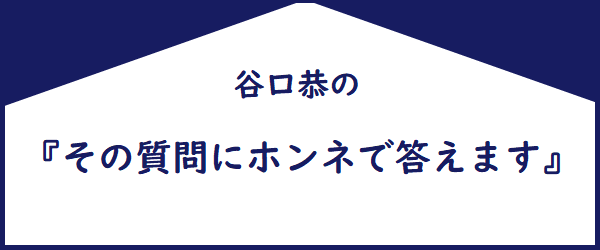マンスリーレポート
2023年8月 開業医は心身が健康である限り引退してはいけない
前々回のコラムでは、医師という職業は患者さんの病の苦痛を引き受け続けなければならないことから"幸せ"にはなれない、という私見を述べました。
「職場のストレスがひどくて......」と訴える患者さんに対し、私は「オン・オフを上手く切り替えましょう」と助言することがあります。つまり、退社時刻になれば仕事のことはきれいさっぱり忘れてプライベートを楽しみましょう、とアドバイスしているのです。
ですが、患者さんが医師の場合(あるいは看護師など他の医療者の場合も)はこのようなことを言いません。私自身がオン・オフを切り替えることができないからです。前回のコラムで述べたように、患者さんの苦痛を忘れることはできません。さらに、あくまでも私見ですが「忘れるべきではない」と考えています。
たいていの医師は、医師という職業を辞めず、医師以外の職業に転職する医師はわずかしかいません。また、早期リタイヤする医師も少数で、80代の医師も何ら珍しくはありません。「もういい年齢だから余生をゆっくり楽しみたい」と言って引退しても、そのうち医療の現場に戻ってくる医師もいます。もちろん、いったん引退したけれども再び仕事を始めるという人は他の業界でも珍しくありませんし、谷口医院の患者さんのなかにも少なくありません。ですが、「職業を替えず、引退もしない職業」をランク付けするとすれば、医師が第1位となるのではないでしょうか。
では、なぜ医師は引退しないのでしょうか。私はこの「答え」を、偶然にも、太融寺町谷口医院を閉院しなければならなくなったことで理解できました。
一般に「人はなぜ働くか」の答えは「生活するため」、つまり「お金を稼ぐため」です。では「一生食べていけるだけのお金があれば引退するか」に対して人はどのように答えるでしょう。「引退する」と答える人もそれなりにいると思います。実際、先述したように引退しても仕事を再開する人がいる一方で、きれいさっぱり仕事はやめて趣味の世界に生きる人もいます。谷口医院の患者さんでいえば、仕事をやめると覇気がなくなる人が多いのですが、なかには「趣味が充実していて楽しくて仕方がない」という人も(少数ではありますが)います。
ですが、ほとんどの人にとって働く理由は「お金のためだけではない」のはあきらかです。上述したように医療者でなくても「いったん退職したけれど再び仕事を始めた」という人はかなりたくさんいますし、引退せずに「可能な限り働き続けたい」という人も少なくありません。谷口医院の患者さんにも大勢います。その理由は「社会とつながっていたい」というものが一番多い気がしますが、「自分がいないと現場が回らないから引退できない」という人もいます。
後者の理由、つまり「自分がいないと......」に対しては、「いずれ引退せねばならないときが来るのだからそれは理由にならないのでは?」という意見があります。むしろ、「引退のタイミングを逃すと"老害"が出てくる」が現実です。
老害はどこの世界にもあると思いますが、医師の世界でもしばしば見受けられます。医師の典型的な老害を感じるのは「学会」です。演者の発表の後の「質疑応答」の場面で手を挙げて、「意味不明の自説」を延々と話し続ける高齢医師がいるのです。座長(司会者)が「時間がおしているのでそろそろ......」と終わらせようとしてもそれでも話をやめない"老害まるだし"の医師もいます。
若い頃活躍していた医師に限って、自身が認知症であると認められず、周囲のスタッフを困らせ、患者さんに迷惑をかけたり、さらに呼ばれていない学会に出掛けたり、頼まれてもいないのに会議に出席しようとしたりすることもあるそうです。
「週刊現代」がある医師の"末路"を負った記事があります。この医師はかつて「天才外科医」の名前をほしいままにしていた、医療者であれば誰もが知っている名医です。記事のなかでは仮名(かめい)が使われていますが、その仮名を見れば医療者ならこの医師が誰なのか容易に推測できます。これだけの名医が認知症となり、そして......。この記事は我々医師にとって最後まで読むのに耐えられないほど辛いものです。
人はいずれ能力が衰えるのですから、あえて早期に引退するのは一種の"美学"だとも言えます。ならば私も早期引退を考えてもいいのではないか。そう思って、太融寺町谷口医院の閉院を決めた1月、タイでボランティアをしながら永住する道やその他引退後のプランを具体的に思案していました。
ところが、私が大好きな西日本のある町で開業する医師から「診療所を引き継いでもらえないか」と言われ、その選択を考えるようになり、その医師から「これまで診てきた患者を見捨てられなくて......」という言葉が私を打ちのめした、という話を前回しました。
閉院を表明した1月以降、私は日々患者さんに「新しいところを紹介しますので閉院を許してください」と言い続けていたわけですが、怒り出したり、泣き出したりする患者さんが後を絶たず、不動産関連の仕事をしている人たちからは「自分が移転先を探しますからなんとか続けてください」などと言われました。なかには不動産業界とは無縁なのに、休日に街を歩いて移転先候補の物件を探してきてくれた患者さんもいました。
そんな患者さんたちを見捨てることなど誰ができるでしょう。では、移転先が見つかったとして(そして幸運にも実際に見つかったわけですが)、私はいつまで医師を続けるべきなのか。この答えはあきらかです。「私の診察を希望する人がいなくなるまで」、そして「私が診療を続けられなくなるほど心身が破壊されるときが来るまで」です。
これが分かった瞬間に「もう一度移転先を探し、そして絶対に見つけなければならない」と決意しました。そして、「老後の楽しみ」とか「引退後の第二の人生」といったものとは自分には縁がないことを自覚し、「私の診察を希望する人がいるのなら、体力、知力、認知力が続く限り診療を続ける」という決心がつきました。
過去のコラム「『偏差値40からの医学部再受験』は間違いだった」でも取り上げたシェークスピアの『As You Like It』に登場するセリフをもう一度紹介したいと思います。
All the world's a stage, and all the men and women merely players. They have their exits and their entrances.(すべての世界は舞台だ。すべての男と女は単に役者を演じているだけだ。我々には初めから出口(退場)と入口(登場)が与えられているのだ)
日本語訳は私によるもので、韻も踏めていないし下手くそな和訳であることは承知していますが、それでも自分の言葉で訳したかったのは、このセリフが「人生の真実」を示していると考えているからです。この世界は誰にとっても"舞台"、そして我々一人一人はその舞台で演じる"役者"なのです。私に与えられた"役"は「体力が続き認知機能が保たれている限り、そして求める人がいる限り診療を続ける」なのです。
それを理解させてくれたのが、谷口医院の「閉院宣言」に反対し、怒り、涙を流し、休日に移転先の物件を探しに行ってくれたような患者さんたちなのです。
「職場のストレスがひどくて......」と訴える患者さんに対し、私は「オン・オフを上手く切り替えましょう」と助言することがあります。つまり、退社時刻になれば仕事のことはきれいさっぱり忘れてプライベートを楽しみましょう、とアドバイスしているのです。
ですが、患者さんが医師の場合(あるいは看護師など他の医療者の場合も)はこのようなことを言いません。私自身がオン・オフを切り替えることができないからです。前回のコラムで述べたように、患者さんの苦痛を忘れることはできません。さらに、あくまでも私見ですが「忘れるべきではない」と考えています。
たいていの医師は、医師という職業を辞めず、医師以外の職業に転職する医師はわずかしかいません。また、早期リタイヤする医師も少数で、80代の医師も何ら珍しくはありません。「もういい年齢だから余生をゆっくり楽しみたい」と言って引退しても、そのうち医療の現場に戻ってくる医師もいます。もちろん、いったん引退したけれども再び仕事を始めるという人は他の業界でも珍しくありませんし、谷口医院の患者さんのなかにも少なくありません。ですが、「職業を替えず、引退もしない職業」をランク付けするとすれば、医師が第1位となるのではないでしょうか。
では、なぜ医師は引退しないのでしょうか。私はこの「答え」を、偶然にも、太融寺町谷口医院を閉院しなければならなくなったことで理解できました。
一般に「人はなぜ働くか」の答えは「生活するため」、つまり「お金を稼ぐため」です。では「一生食べていけるだけのお金があれば引退するか」に対して人はどのように答えるでしょう。「引退する」と答える人もそれなりにいると思います。実際、先述したように引退しても仕事を再開する人がいる一方で、きれいさっぱり仕事はやめて趣味の世界に生きる人もいます。谷口医院の患者さんでいえば、仕事をやめると覇気がなくなる人が多いのですが、なかには「趣味が充実していて楽しくて仕方がない」という人も(少数ではありますが)います。
ですが、ほとんどの人にとって働く理由は「お金のためだけではない」のはあきらかです。上述したように医療者でなくても「いったん退職したけれど再び仕事を始めた」という人はかなりたくさんいますし、引退せずに「可能な限り働き続けたい」という人も少なくありません。谷口医院の患者さんにも大勢います。その理由は「社会とつながっていたい」というものが一番多い気がしますが、「自分がいないと現場が回らないから引退できない」という人もいます。
後者の理由、つまり「自分がいないと......」に対しては、「いずれ引退せねばならないときが来るのだからそれは理由にならないのでは?」という意見があります。むしろ、「引退のタイミングを逃すと"老害"が出てくる」が現実です。
老害はどこの世界にもあると思いますが、医師の世界でもしばしば見受けられます。医師の典型的な老害を感じるのは「学会」です。演者の発表の後の「質疑応答」の場面で手を挙げて、「意味不明の自説」を延々と話し続ける高齢医師がいるのです。座長(司会者)が「時間がおしているのでそろそろ......」と終わらせようとしてもそれでも話をやめない"老害まるだし"の医師もいます。
若い頃活躍していた医師に限って、自身が認知症であると認められず、周囲のスタッフを困らせ、患者さんに迷惑をかけたり、さらに呼ばれていない学会に出掛けたり、頼まれてもいないのに会議に出席しようとしたりすることもあるそうです。
「週刊現代」がある医師の"末路"を負った記事があります。この医師はかつて「天才外科医」の名前をほしいままにしていた、医療者であれば誰もが知っている名医です。記事のなかでは仮名(かめい)が使われていますが、その仮名を見れば医療者ならこの医師が誰なのか容易に推測できます。これだけの名医が認知症となり、そして......。この記事は我々医師にとって最後まで読むのに耐えられないほど辛いものです。
人はいずれ能力が衰えるのですから、あえて早期に引退するのは一種の"美学"だとも言えます。ならば私も早期引退を考えてもいいのではないか。そう思って、太融寺町谷口医院の閉院を決めた1月、タイでボランティアをしながら永住する道やその他引退後のプランを具体的に思案していました。
ところが、私が大好きな西日本のある町で開業する医師から「診療所を引き継いでもらえないか」と言われ、その選択を考えるようになり、その医師から「これまで診てきた患者を見捨てられなくて......」という言葉が私を打ちのめした、という話を前回しました。
閉院を表明した1月以降、私は日々患者さんに「新しいところを紹介しますので閉院を許してください」と言い続けていたわけですが、怒り出したり、泣き出したりする患者さんが後を絶たず、不動産関連の仕事をしている人たちからは「自分が移転先を探しますからなんとか続けてください」などと言われました。なかには不動産業界とは無縁なのに、休日に街を歩いて移転先候補の物件を探してきてくれた患者さんもいました。
そんな患者さんたちを見捨てることなど誰ができるでしょう。では、移転先が見つかったとして(そして幸運にも実際に見つかったわけですが)、私はいつまで医師を続けるべきなのか。この答えはあきらかです。「私の診察を希望する人がいなくなるまで」、そして「私が診療を続けられなくなるほど心身が破壊されるときが来るまで」です。
これが分かった瞬間に「もう一度移転先を探し、そして絶対に見つけなければならない」と決意しました。そして、「老後の楽しみ」とか「引退後の第二の人生」といったものとは自分には縁がないことを自覚し、「私の診察を希望する人がいるのなら、体力、知力、認知力が続く限り診療を続ける」という決心がつきました。
過去のコラム「『偏差値40からの医学部再受験』は間違いだった」でも取り上げたシェークスピアの『As You Like It』に登場するセリフをもう一度紹介したいと思います。
All the world's a stage, and all the men and women merely players. They have their exits and their entrances.(すべての世界は舞台だ。すべての男と女は単に役者を演じているだけだ。我々には初めから出口(退場)と入口(登場)が与えられているのだ)
日本語訳は私によるもので、韻も踏めていないし下手くそな和訳であることは承知していますが、それでも自分の言葉で訳したかったのは、このセリフが「人生の真実」を示していると考えているからです。この世界は誰にとっても"舞台"、そして我々一人一人はその舞台で演じる"役者"なのです。私に与えられた"役"は「体力が続き認知機能が保たれている限り、そして求める人がいる限り診療を続ける」なのです。
それを理解させてくれたのが、谷口医院の「閉院宣言」に反対し、怒り、涙を流し、休日に移転先の物件を探しに行ってくれたような患者さんたちなのです。