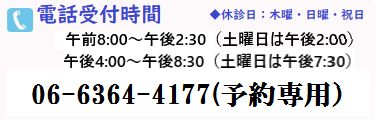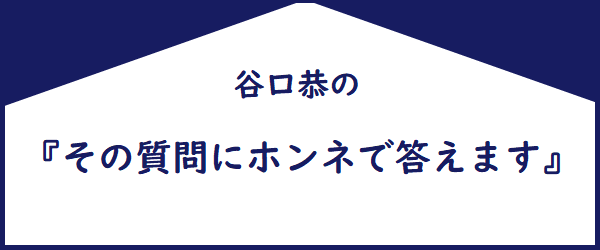依存症を治す! 不眠・抑うつ・不安・他
数年前より依存症の相談がますます増えています。最も多いのは「(他院で処方されている)睡眠薬などのベンゾジアゼピン系の依存症を治したい」で、現在は「睡眠薬の処方を希望」の数を凌いでいます。また、最近は「市販の咳止め・風邪薬をやめたいけどやめられない」という訴えが増えています。覚醒剤を中心とする違法薬物の相談にも以前と変わらず応じています。アルコールについては禁酒ではなく「節酒」のケースでは「セリンクロ」の処方をおこないます。買い物依存、摂食障害、ギャンブル依存、性依存なども、他に行くところがない人たちから相談を受けています。依存症は以前から、そして現在も、精神科受診のみならず自助グループへの参加を試みてもらうようにしていますが、希望される方は当院で診察いたします。不眠・抑うつ・不安といった精神症状を希望があれば診察いたします。
★アルコールの量を減らしたい、またはやめたい
参考:はやりの病気第246回(2024年2月)「我々は飲酒を完全にやめるべきか」
★禁煙したい
注:現在処方できる薬は貼付薬の「ニコチネル」のみです。ファイザー製薬によると飲み薬の「チャンピックス」は依然製造中止が続いています。
★ベンゾジアゼピン(睡眠薬・抗不安薬)をやめたい
参考:
はやりの病気第164回(2017年4月)「本当に危険なベンゾジアゼピン依存症」
はやりの病気第124回(2013年12月)「睡眠薬の恐怖」
「健康づくりのための睡眠指針 2014 ~ 睡眠12箇条 ~」
「乱用されていた睡眠薬・抗不安薬」(出典は厚労省の実態調査)
★市販の咳止め・風邪薬をやめたい
・厚労省が指定する咳止め・風邪薬に含まれている「6つの危険な成分」は下記の通りです。
#1 エフェドリン
#2 メチルエフェドリン
#3 プソイドエフェドリン
#4 コデイン
#5 ジヒドロコデイン
#6 ブロムワレリル尿素
参考:
日経メディカル(2020年6月30日)「悪名高いOTC鎮痛薬、販売継続の謎」
「乱用されていた市販薬」(出典は厚労省の実態調査)
「依存性の強い薬物が入っている市販薬」
★大麻をやめたい、減らしたい
参考:GINAと共に
第211回(2024年1月)「大麻に手を出してはいけない「3つ目の理由」」
第210回(2023年12月) 「大麻について現時点で分かっている科学的知見」
★覚醒剤、麻薬、コカイン、LSD、その他の違法薬物をやめたい
精神科受診や自助グループの利用に抵抗がある、あるいはすでにそういった治療を試みたけれどうまくいかなかったような場合はご相談ください。
★摂食障害
まずは下記のリストにある医療機関受診を勧めますが、うまくいかない場合は当院で診察いたします。
摂食障害治療施設リスト2022年版
★その他依存症(ギャンブル依存、買い物依存、性依存など行動嗜癖を含む)
精神科受診、自助グループなどをまずは勧めますが、そういった治療に抵抗があったり、試したけれどよくならなかったという場合はご相談ください。
★不眠・抑うつ・不安・その他
精神科に抵抗がある、精神科を受診したけれどよくならなかった、という方はご相談ください。
更新:2024年2月11日
「かかりつけ医をもとう」
花粉症対策 / アレルギーの検査 / のどの痛み(咽頭痛) / インフルエンザ / 湿疹・かぶれ・じんましん / 生活習慣病・メタボリックシンドローム / アトピーを治そう / 片頭痛を治そう / 長引く咳(せき) / 不眠を治そう / ぜんそく / 予防接種をしよう / ニキビ・酒さ(しゅさ)を治そう / HIV検査(抗体・NAT)・性感染症・血液感染症 / 水虫がはやっています! / ED(勃起不全)を克服する / 肝炎ワクチンの接種をしよう / 薄毛・抜け毛を治そう / 禁煙外来 / 旅行医学・英文診断書など